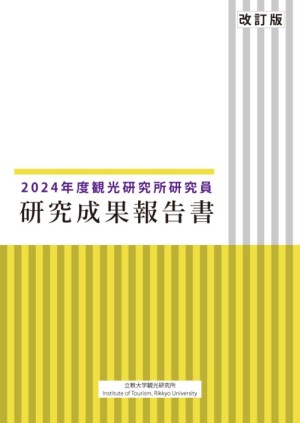観光研究所Institute of Tourism

観光研究所は、わが国および諸外国の観光事象と関連産業全般について理論的及び実践的観点から研究するとともに、その成果をもって観光の発展に貢献することを目的としています。
研究所について
「ホテル講座」の開設
立教大学観光研究所の起源は、第二次世界大戦終結直後の1946(昭和21)年に開設された「ホテル講座」にさかのぼる。「ホテル講座」は、戦後の日本の復興を、平和産業である観光で支えたいという学生たちの願いに対して、観光を担う若い人たちの育成のためにと、本学卒業生で箱根宮ノ下・富士屋ホテルの3代目社長であった故山口正造氏の記念育英資金により、寄付講座として始まった。課外講座とはいえアジアで初めての観光・ホスピタリティ教育プログラムであり、開設当初から、本学の学生だけでなく、他大学の学生や社会人にも広く門戸を開いた「公開講座」として運営され、多くの人材を輩出してきた。
観光研究所の設立
1960年、「ホテル講座」は大学の正課外講座の一つとして位置づけられ、社会学部所管となった。カリキュラムを抜本的に見直して観光事業関連講義を強化し、講師や運営の刷新を図って、1961年に講座名を「観光・ホテル講座」に改称した。
1964年の「東京オリンピック」開催を契機に、ホテルおよび観光に関する高等教育・研究機関設置を求める声が高まったことを受け、1966年社会学部産業関係学科に「ホテル・観光課程」が開設され、それに併せて講座名を「ホテル・観光講座」に改称した。
1967年にはわが国4年制大学における最初の観光教育機関として、社会学部に「観光学科」が設置され、同時に、「ホテル・観光講座」の運営、および観光に関する研究・調査等をおこなう機関として「立教大学観光研究所」が設立された。
1964年の「東京オリンピック」開催を契機に、ホテルおよび観光に関する高等教育・研究機関設置を求める声が高まったことを受け、1966年社会学部産業関係学科に「ホテル・観光課程」が開設され、それに併せて講座名を「ホテル・観光講座」に改称した。
1967年にはわが国4年制大学における最初の観光教育機関として、社会学部に「観光学科」が設置され、同時に、「ホテル・観光講座」の運営、および観光に関する研究・調査等をおこなう機関として「立教大学観光研究所」が設立された。
講座の改編と新たな歩み
その後、観光研究所は、時代の要請に合わせ、より新しくより実践的な観光・ホスピタリティ教育をめざして講座の拡充を図り、現在では、研究所の原点である「ホテル講座」の伝統を引き継ぐ「ホスピタリティ・マネジメント講座」、国家試験である旅行業務取扱管理者の資格取得を目指す「旅行業講座」、そして地域経営の視点から観光地づくりを担う人材の育成を目的とした「観光地経営専門家育成プログラム」を加えた3つの講座を運営するに至っている。これからも「わが国の観光を担う人材の育成」という観光研究所の使命を果たすべく、講座のより一層の充実を図っていきたい。
わが国および諸外国の観光事象と関連産業全般について理論的及び実践的観点から研究するとともに、その成果をもって観光の発展に貢献することを目的としており、この目的を達成するために、次の各事業を行う(観光研究所規則による)。
- 観光に関する基礎的ならびに応用的調査・研究の実施
- 内外からの研修員の受入れならびに指導
- 関係図書・資料の収集保管ならびに内外の要請による情報提供
- 研究会・講演会等の開催
- 公開講座の管理・運営
所長
橋本 俊哉(観光学部教授)
副所長
庄司 貴行(観光学部教授)
所員
東 徹(観光学部教授)
石橋 正孝(観光学部教授)
大橋 健一(観光学部教授)
小野 良平(観光学部教授)
風間 欣人(観光学部特任教授)
門田 岳久(観光学部教授)
川嶋 久美子(観光学部准教授)
韓 志昊(観光学部教授)
葛野 浩昭(観光学部教授)
久保 忠行(観光学部教授)
毛谷村 英治(観光学部教授)
斎藤 明(観光学部教授)
佐藤 大祐(観光学部教授)
沢柳 知彦(観光学部特任教授)
竺 佳庚(観光学部特任准教授)
千住 一(観光学部教授)
高岡 文章(観光学部教授)
杜 国慶(観光学部教授)
西川 亮(観光学部准教授)
野田 健太郎(観光学部教授)
野原 克仁(観光学部教授)
羽生 冬佳(観光学部教授)
舛谷 鋭(観光学部教授)
松村 公明(観光学部教授)
小沢 健市(立教大学名誉教授)
田代 泰久(立教大学名誉教授)
豊田 由貴夫(立教大学名誉教授)
前田 勇(立教大学名誉教授)
溝尾 良隆(立教大学名誉教授)
村上 和夫(立教大学名誉教授)
安島 博幸(立教大学名誉教授)
顧問
蒲生 篤実(日本政府観光局 理事長)
最明 仁(公益社団法人日本観光振興協会 理事長)
高橋 広行(一般社団法人日本旅行業協会 会長)
定保 英弥(一般社団法人日本ホテル協会 会長)
桑野 和泉(一般社団法人日本旅館協会 会長)
浅野 一行(公益社団法人国際観光施設協会 会長)
多田 計介(一般社団法人日本温泉協会 会長)
参与
掛江 浩一郎(一般社団法人日本ホテル協会 専務理事)
有野 一馬(一般社団法人全日本ホテル連盟 専務理事)
青木 幸裕(一般社団法人日本旅館協会 専務理事)
特任研究員
井上 晶子
玉井 和博
研究員
李 彰美
大川 朝子
田中 真知
羽生 敦子
橋本 俊哉(観光学部教授)
副所長
庄司 貴行(観光学部教授)
所員
東 徹(観光学部教授)
石橋 正孝(観光学部教授)
大橋 健一(観光学部教授)
小野 良平(観光学部教授)
風間 欣人(観光学部特任教授)
門田 岳久(観光学部教授)
川嶋 久美子(観光学部准教授)
韓 志昊(観光学部教授)
葛野 浩昭(観光学部教授)
久保 忠行(観光学部教授)
毛谷村 英治(観光学部教授)
斎藤 明(観光学部教授)
佐藤 大祐(観光学部教授)
沢柳 知彦(観光学部特任教授)
竺 佳庚(観光学部特任准教授)
千住 一(観光学部教授)
高岡 文章(観光学部教授)
杜 国慶(観光学部教授)
西川 亮(観光学部准教授)
野田 健太郎(観光学部教授)
野原 克仁(観光学部教授)
羽生 冬佳(観光学部教授)
舛谷 鋭(観光学部教授)
松村 公明(観光学部教授)
小沢 健市(立教大学名誉教授)
田代 泰久(立教大学名誉教授)
豊田 由貴夫(立教大学名誉教授)
前田 勇(立教大学名誉教授)
溝尾 良隆(立教大学名誉教授)
村上 和夫(立教大学名誉教授)
安島 博幸(立教大学名誉教授)
顧問
蒲生 篤実(日本政府観光局 理事長)
最明 仁(公益社団法人日本観光振興協会 理事長)
高橋 広行(一般社団法人日本旅行業協会 会長)
定保 英弥(一般社団法人日本ホテル協会 会長)
桑野 和泉(一般社団法人日本旅館協会 会長)
浅野 一行(公益社団法人国際観光施設協会 会長)
多田 計介(一般社団法人日本温泉協会 会長)
参与
掛江 浩一郎(一般社団法人日本ホテル協会 専務理事)
有野 一馬(一般社団法人全日本ホテル連盟 専務理事)
青木 幸裕(一般社団法人日本旅館協会 専務理事)
特任研究員
井上 晶子
玉井 和博
研究員
李 彰美
大川 朝子
田中 真知
羽生 敦子
研究所からのお知らせ
2026年度旅行業講座の日程と募集要項を以下のページに掲載いたしました。
最新号Vol.21は下のリンクからご覧いただけます。
2025年度ホスピタリティ・マネジメント講座の日程と募集要項を以下のページに掲載いたしました。
詳細について、下記リンクからご覧ください。

ホスピタリティ産業界の人材育成に向けて、観光学を学びたいと考える全国の高校2年生を対象に、「立教箱根・ツーリズム・ハイスクール」を下記のとおり開催いたします。
申込期間は2025年7月1日(火)~7月8日(火)13:00までです。
申込期間は2025年7月1日(火)~7月8日(火)13:00までです。
2025年4月1日に観光研究所主催の公開講座についてのガイダンスを実施致しました。
講座・プログラム
旅行会社では各営業所に「旅行業務取扱管理者」を置くことが旅行業法で定められています。国家資格である「総合旅行業務取扱管理者試験」や「国内旅行業務取扱管理者試験」を受験する上で必要な、旅行業務を取り扱うための基礎となる各種の実務知識や関係法令などについて実践的な講義を行います。
宿泊産業を中心とするホスピタリティ産業の経営実務全般に関する知識を、効果的かつ理論的に学ぶための講座です。マーケティング、人事、財務、法規など多岐にわたる各分野の専門家・経営陣が分かりやすく講義します。
観光による地域振興を図るためには、変化する観光の動向を的確にとらえ、観光地を革新し、マネジメントする能力をもった人材が求められます。この講座では、そうした知識・スキルをもった人材=観光地経営専門家を育成することを目標とした知識の習得と、観光地経営に必要とされる調査分析方法について学びます。
刊行物
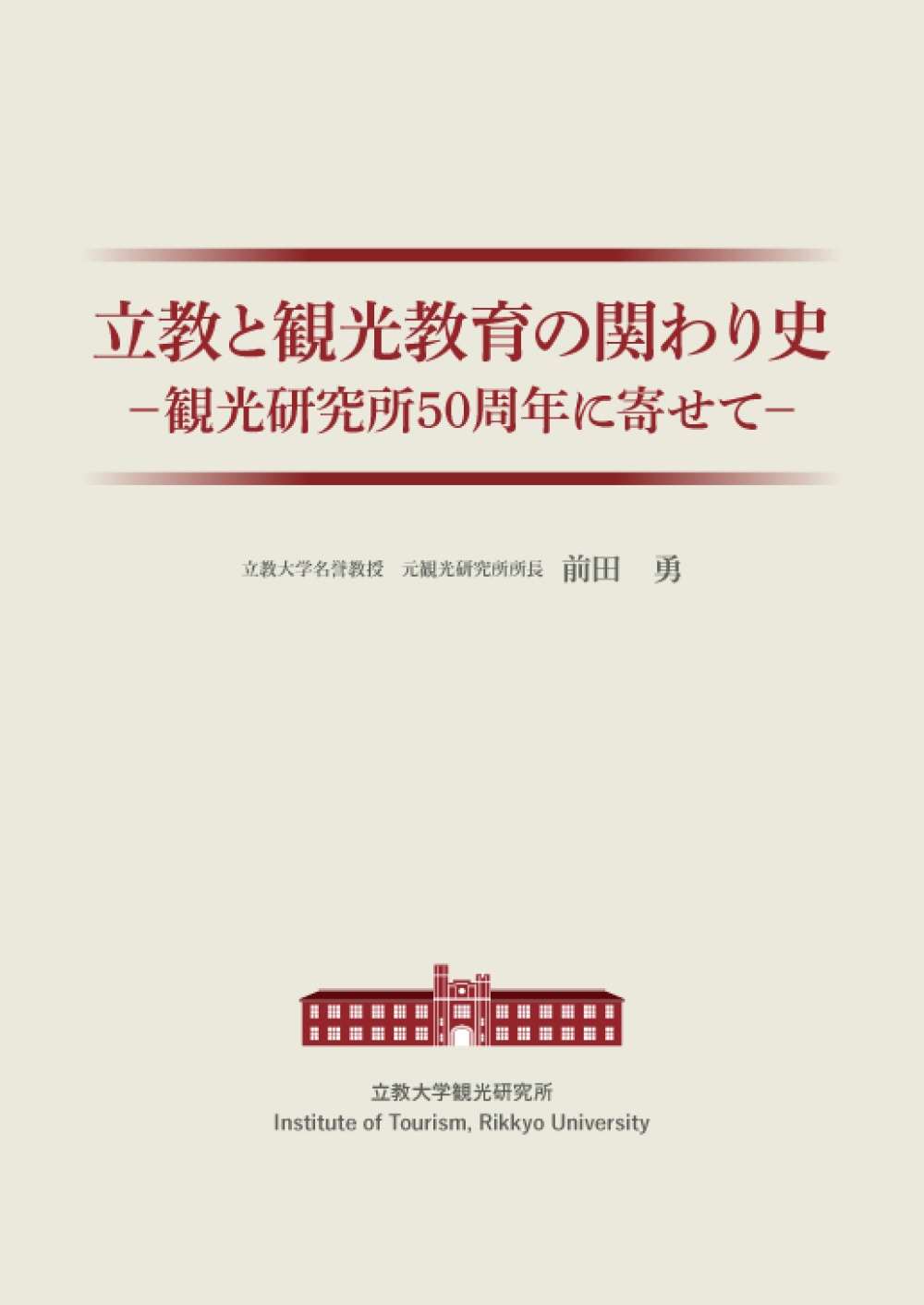
本誌は、観光研究所開設50周年を記念して開催されたシンポジウムに際し、本学名誉教授である前田 勇先生に「立教と観光教育の関わり」についてお話しいただいた講演内容を収録したものです。“さまざまなエピソード”を紹介することを通して立教の観光に関する教育史を語ると共に日本における観光発展史についても語られています。貴重な記録として、後に続く世代に伝えていくことを目的として刊行いたしました。是非ご覧ください。
観光研究所では2004年以降「観光研究所だより」を発行しており、さまざまな活動を記録しています。
下記のリンクで、第1号から最新号までご覧いただけます。
下記のリンクで、第1号から最新号までご覧いただけます。
講演会・シンポジウム
開催日程:
2021年11月26日(金)18:30~20:30
内容:
観光の産業としての価値や将来性等をわかりやすく発信し、都民の観光振興への理解を促進することを目的としたシンポジウムを開催する。観光による経済効果や観光振興推進の意義・メリット等について再確認するとともに、池上彰氏をファシリテーターとして、「“観光地としての東京”の将来」をテーマに東京の魅力を再発見する。
トークテーマ① 東京経由はおもしろい ~東京で生まれる新たな価値~
トークテーマ② 東京に来れば世界がわかる ~多様性に溢れた都市 東京~
トークテーマ③ コロナ後の観光 ~観光振興の影響・メリット~
パネリスト:
池上 彰氏(立教大学客員教授)
宮田 崇氏(株式会社地球の歩き方 『地球の歩き方』編集長)
工藤 里紗氏(株式会社テレビ東京プロデューサー)
村上 和夫氏(立教大学名誉教授) 他
アシスタント:
角谷 暁子氏(株式会社テレビ東京アナウンサー)
開催場所:
オンライン開催(YouTube LIVE および LINELIVE)
対象者:
都内に在住・在勤または在学の方(定員はありません)
参加費:
無料
申込期間:
2021年11月11日(木)~2021年11月25日(木)
お問い合わせ:
ritourism@rikkyo.ac.jp
シンポジウムの当日の模様を動画にて公開しております。 公開期間:12月3日18:00まで
2021年11月26日(金)18:30~20:30
内容:
観光の産業としての価値や将来性等をわかりやすく発信し、都民の観光振興への理解を促進することを目的としたシンポジウムを開催する。観光による経済効果や観光振興推進の意義・メリット等について再確認するとともに、池上彰氏をファシリテーターとして、「“観光地としての東京”の将来」をテーマに東京の魅力を再発見する。
トークテーマ① 東京経由はおもしろい ~東京で生まれる新たな価値~
トークテーマ② 東京に来れば世界がわかる ~多様性に溢れた都市 東京~
トークテーマ③ コロナ後の観光 ~観光振興の影響・メリット~
パネリスト:
池上 彰氏(立教大学客員教授)
宮田 崇氏(株式会社地球の歩き方 『地球の歩き方』編集長)
工藤 里紗氏(株式会社テレビ東京プロデューサー)
村上 和夫氏(立教大学名誉教授) 他
アシスタント:
角谷 暁子氏(株式会社テレビ東京アナウンサー)
開催場所:
オンライン開催(YouTube LIVE および LINELIVE)
対象者:
都内に在住・在勤または在学の方(定員はありません)
参加費:
無料
申込期間:
2021年11月11日(木)~2021年11月25日(木)
お問い合わせ:
ritourism@rikkyo.ac.jp
シンポジウムの当日の模様を動画にて公開しております。 公開期間:12月3日18:00まで
■日時
2018年1月20日(土)14:00~16:15
■場所
立教大学 池袋キャンパス7号館1階 7102教室
■内容
観光研究所が今年度開設50周年を迎えたことを記念してシンポジウムを開催する。1995~2000年度まで観光研究所所長を務められ、このたび瑞宝中綬章を受章された前田勇本学名誉教授に基調講演をいただき、続いて観光研究所と縁の深い方々に観光の過去・現在・未来、さらにはこれからの観光研究所のあり方について語っていただく。
■講師
基調講演 前田 勇 氏(本学名誉教授)
パネリスト 小田 真弓 氏(加賀屋女将)
岡本 伸之 氏(本学名誉教授)
安島 博幸 氏(本学名誉教授)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
観光研究所関係者、本学学生及び教職員、一般
※事前申込不要、参加費無料
■問合せ先
立教大学観光研究所事務局 小林(電話:03-3985-2577、e-mail: kanken@rikkyo.ac.jp)
2018年1月20日(土)14:00~16:15
■場所
立教大学 池袋キャンパス7号館1階 7102教室
■内容
観光研究所が今年度開設50周年を迎えたことを記念してシンポジウムを開催する。1995~2000年度まで観光研究所所長を務められ、このたび瑞宝中綬章を受章された前田勇本学名誉教授に基調講演をいただき、続いて観光研究所と縁の深い方々に観光の過去・現在・未来、さらにはこれからの観光研究所のあり方について語っていただく。
■講師
基調講演 前田 勇 氏(本学名誉教授)
パネリスト 小田 真弓 氏(加賀屋女将)
岡本 伸之 氏(本学名誉教授)
安島 博幸 氏(本学名誉教授)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
観光研究所関係者、本学学生及び教職員、一般
※事前申込不要、参加費無料
■問合せ先
立教大学観光研究所事務局 小林(電話:03-3985-2577、e-mail: kanken@rikkyo.ac.jp)
■日時
2017年12月5日(火)17:00~20:30
■場所
立教大学池袋キャンパス 7号館7101教室
■内容
食と観光の密接な関係は広く知られてきたところである。一方で、土地に根差す食材や食文化を見直し、食の多様性を堅持しようとする「スローフード」と呼ばれる運動がイタリアで発祥し、そうした考えが徐々に世界に伝播している。食材の産地と消費者、さらには料理人や研究者を結び付け、食の知恵と技術の交流を促す役割が観光に新たに期待されるようになってきている。
本講演会では、食科学(Gastronomic Science)と呼ばれる近年注目されるこの分野の内容を具体的に整理しながら、観光が食の新しい運動から何を学ぶべきなのか、一方で食の分野では観光と今後どのような関係を構築するのか、食というフィールドにおける産学連携の新たな枠組みを構想しながら、食科学と観光の今後の関係性について議論する。
■講師
齋藤 由佳子 氏(Genuine Education Network代表)
尾藤 環 氏(辻調理師専門学校 企画部長・産学連携教育推進室長)
阿部 尚行 氏(経済産業省商務情報政策局サービス政策課課長補佐)(追加)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
学生、大学院生、教職員、一般
■申込
氏名、職業(所属)、連絡先メールアドレスを明記の上、visitor@ml.rikkyo.ac.jp までお申し込みください。
■問合せ
庄司 貴行(立教大学観光学部観光学科教授、tashoji@rikkyo.ac.jp)
2017年12月5日(火)17:00~20:30
■場所
立教大学池袋キャンパス 7号館7101教室
■内容
食と観光の密接な関係は広く知られてきたところである。一方で、土地に根差す食材や食文化を見直し、食の多様性を堅持しようとする「スローフード」と呼ばれる運動がイタリアで発祥し、そうした考えが徐々に世界に伝播している。食材の産地と消費者、さらには料理人や研究者を結び付け、食の知恵と技術の交流を促す役割が観光に新たに期待されるようになってきている。
本講演会では、食科学(Gastronomic Science)と呼ばれる近年注目されるこの分野の内容を具体的に整理しながら、観光が食の新しい運動から何を学ぶべきなのか、一方で食の分野では観光と今後どのような関係を構築するのか、食というフィールドにおける産学連携の新たな枠組みを構想しながら、食科学と観光の今後の関係性について議論する。
■講師
齋藤 由佳子 氏(Genuine Education Network代表)
尾藤 環 氏(辻調理師専門学校 企画部長・産学連携教育推進室長)
阿部 尚行 氏(経済産業省商務情報政策局サービス政策課課長補佐)(追加)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
学生、大学院生、教職員、一般
■申込
氏名、職業(所属)、連絡先メールアドレスを明記の上、visitor@ml.rikkyo.ac.jp までお申し込みください。
■問合せ
庄司 貴行(立教大学観光学部観光学科教授、tashoji@rikkyo.ac.jp)
■日時
2016年8月25日(木)15:00~18:00
■場所
立教大学池袋キャンパス マキムホールM301教室(3階)
■内容
2015年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の1974万人に達し、政府は、さらに、その目標値を、2020年に4000万人、2030年に6000万人と拡大しました。しかし、このインバウンド急増の裏で、中国人訪日観光ツアーの爆買いや無資格ガイド、営業許可を受けない民泊による近隣トラブル等の問題がクローズアップされてきています。本セミナーでは、これらの問題の実態を見据え、我が国の観光のあるべき姿を探っていこうと思います。
■プログラム・講師
(1)「インバウンド新時代—問題提起—」橋本俊載(立教大学観光学部教授)
(2)「訪日中国人観光客の動向」立教大学観光学部東ゼミ:学生レポート
(3)「インバウンドにおけるランドオペレーターの機能と規制に関する諸問題」小池修司(弁護士・立教大学兼任講師)
(4)「インバウンド急増にともなう民泊問題」薬師丸正二郎(立教大学法学部特任准教授)
(5)「観光立国への課題」東 徹(立教大学観光学部教授・観光研究所長)
■企画
川添 利賢(立教大学法務研究科特任教授)<進行役>
畑 敬(弁護士・立教大学兼任講師)
■主催
立教大学観光ADRセンター
■共催
立教大学法務研究科、立教大学観光研究所
■申込
不要
■対象
本学学生、教職員、校友、一般
■問合せ
立教大学観光ADRセンター(03-3985-4650)
2016年8月25日(木)15:00~18:00
■場所
立教大学池袋キャンパス マキムホールM301教室(3階)
■内容
2015年の訪日外国人旅行者数は、過去最高の1974万人に達し、政府は、さらに、その目標値を、2020年に4000万人、2030年に6000万人と拡大しました。しかし、このインバウンド急増の裏で、中国人訪日観光ツアーの爆買いや無資格ガイド、営業許可を受けない民泊による近隣トラブル等の問題がクローズアップされてきています。本セミナーでは、これらの問題の実態を見据え、我が国の観光のあるべき姿を探っていこうと思います。
■プログラム・講師
(1)「インバウンド新時代—問題提起—」橋本俊載(立教大学観光学部教授)
(2)「訪日中国人観光客の動向」立教大学観光学部東ゼミ:学生レポート
(3)「インバウンドにおけるランドオペレーターの機能と規制に関する諸問題」小池修司(弁護士・立教大学兼任講師)
(4)「インバウンド急増にともなう民泊問題」薬師丸正二郎(立教大学法学部特任准教授)
(5)「観光立国への課題」東 徹(立教大学観光学部教授・観光研究所長)
■企画
川添 利賢(立教大学法務研究科特任教授)<進行役>
畑 敬(弁護士・立教大学兼任講師)
■主催
立教大学観光ADRセンター
■共催
立教大学法務研究科、立教大学観光研究所
■申込
不要
■対象
本学学生、教職員、校友、一般
■問合せ
立教大学観光ADRセンター(03-3985-4650)
■日時
2016年5月13日(金)18:30~20:00
■場所
立教大学池袋キャンパス12号館地下1階 第1・2会議室
■講師
Tadayuki Hara(原 忠之)氏 (立教大学招へい研究員、セントラルフロリダ大学ホスピタリティ経営学部准教授(アメリカ合衆国))
■司会
豊田 由貴夫(立教大学観光学部教授、観光研究所所員)
■内容
昨年、訪日外国人観光客数は1974万人となり、3年間で2倍以上となった。これを受けて今年3月、政府はこの訪日外国人観光客数を2030年までに6000万人にするという目標を掲げた。この目標は可能なのか、またこの目標を達成するために日本は何をすべきなのか、どのようなことが必要なのかを考える。
■言語
英語(通訳なし)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
本学教職員、学生、一般
■問合せ先
豊田 由貴夫(e-mail: ytoyoda@rikkyo.ac.jp)
2016年5月13日(金)18:30~20:00
■場所
立教大学池袋キャンパス12号館地下1階 第1・2会議室
■講師
Tadayuki Hara(原 忠之)氏 (立教大学招へい研究員、セントラルフロリダ大学ホスピタリティ経営学部准教授(アメリカ合衆国))
■司会
豊田 由貴夫(立教大学観光学部教授、観光研究所所員)
■内容
昨年、訪日外国人観光客数は1974万人となり、3年間で2倍以上となった。これを受けて今年3月、政府はこの訪日外国人観光客数を2030年までに6000万人にするという目標を掲げた。この目標は可能なのか、またこの目標を達成するために日本は何をすべきなのか、どのようなことが必要なのかを考える。
■言語
英語(通訳なし)
■主催
立教大学観光研究所
■対象
本学教職員、学生、一般
■問合せ先
豊田 由貴夫(e-mail: ytoyoda@rikkyo.ac.jp)
お問い合わせ
立教大学観光研究所
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学12号館2F 総合研究センター内
電話:03-3985-2577
Fax:03-3985-0279(「観光研究所宛」と明記してください)
メール:kanken@rikkyo.ac.jp
※在宅勤務とキャンパス勤務を併用しているため、お問合せはメールでお願いいたします。
電話:03-3985-2577
Fax:03-3985-0279(「観光研究所宛」と明記してください)
メール:kanken@rikkyo.ac.jp
※在宅勤務とキャンパス勤務を併用しているため、お問合せはメールでお願いいたします。
※各講座の詳細は下記リンクからご覧いただけます。
旅行業講座はこちら