大学の学びを体験 地方都市再生のまちづくり学
——立教大学×三条高等学校
立教大学特別授業
2025/09/30
研究活動と教授陣
OVERVIEW
7月1日、大学の講義を高校生が体験する「立教大学特別授業」が新潟県立三条高等学校で行われた。人文地理学・まちづくり論を専門とする武者忠彦教授による講義で、参加した全校生徒約720人は大学での専門的な学びと雰囲気を体験。従来のまちづくりから「まちづかい」への転換という新しい視点を通じて、地域の可能性やライフコースについて考えを深める機会となった。

武者 忠彦 教授
1975年長野県佐久市生まれ、東京大学理学部卒業後、メーカー勤務を経て東京大学で博士号を取得。信州大学経済学部を経て2023年より現職。長野県住宅審議会会長も務める。専攻は人文地理学、まちづくり論。
「まちづくり」とは何かを考える

まちづくりについて語る武者教授
人生の歩み方の変化と大都市圏への人口集中

しかし現在、このライフコースは劇的に変化しています。例えば1950年頃に生まれた女性の約8割は結婚・出産・専業主婦を経験していましたが、現代ではそのような標準的なライフコースは大幅に縮小し、多様な生き方が選択されるようになりました。その延長線上に、二拠点居住、ワーケーション、デジタルノマド、関係人口など、地方における新しい働き方や暮らし方も登場しています。
従来のまちづくりから「まちづかい」へ

約720人が参加した特別授業の様子
ところが、日本が人口減少社会に転じると、近代化によってまちを新たにつくりだす「まちづくり」の必要はなくなり、それに代わって、既にあるまちを利活用する「まちづかい」が必要となってきました。人口増加により市場が拡大するまちづくりの時代は、他の都市と同じような計画を立てて、新しさや便利さを追求する近代化は「勝ち馬に乗る」戦略でした。ところが、人口減少によって市場が縮小していくまちづかいの時代になると、同じように近代化していく方法は一転して「泥舟に乗る」戦略になってしまいます。そこで求められるのは、他の都市と差別化して固有の価値(つまり地域性)を生み出し、何とか生き延びようとする戦略です。まちづかいの時代に、このように地域性を高めて持続可能な都市を追求することを、私は「文脈化」とよんでいます。
地域の文脈を生かす新しいまちづくり
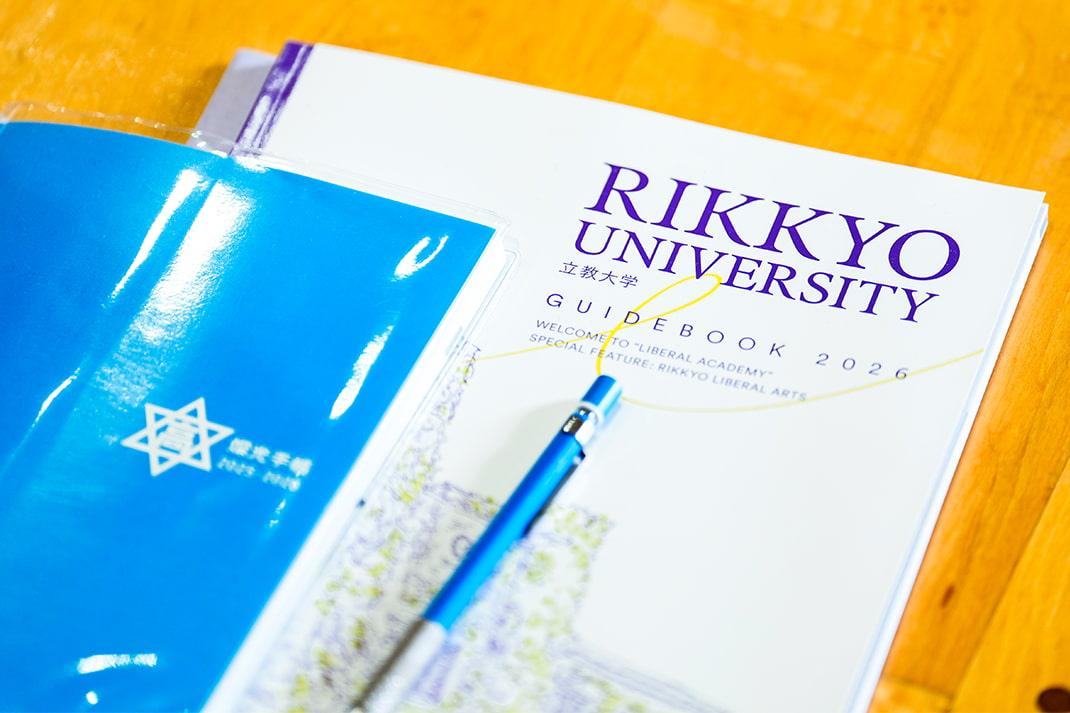
参加した高校生の声
1年生男子
講義を聞いて、地元を大切にしながら外の世界に触れることも重要だと感じました。将来は起業して新潟を盛り上げる仕事をしたいと考えています。新潟の良さを発信するためにも、さまざまなアイデアを得ていきたいです。
1年生女子
授業で地方創生をテーマに調べていたため、今回の講義はとても参考になりました。家族が受験生で県外への進学を検討中のため、一極集中の課題についても考えさせられましたし、将来を考えるきっかけにもなりました。
2年生男子
親族に教職員が多いこともあり、教職員を目指していましたが、大学には多様なコースや学びがあることを改めて知りました。選択肢の多さで視野も広がりました。今後は地元で働くことの意味も考えていきたいです。
2年生女子
家族がずっと新潟にいるため、自分も残ると漠然と考えていました。講義を聞いて、県外の取り組みを学んで新潟に生かすことの大切さや、一度外に出て新しい視点で新潟を見ることも必要だと思いました。
3年生男子
講義を通して、将来は三条市に残ってものづくりを生かした活性化に携わりたいという思いが強くなりました。地域を盛り上げる活動をしている方々に学び、地域に関する取り組みにも積極的に参加していきたいです。
3年生女子
探究活動で地方創生を研究中で、今あるものの魅力を発信するという点で、講義内容がリンクする点がたくさんありました。進学は立教大学を目指しています。将来は地元燕市に戻って国際教育に携わりたいです。
※記事の内容は取材時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。
CATEGORY
このカテゴリの他の記事を見る
研究活動と教授陣
2026/02/20
AI活用時代の学び~探究の学習とリーダーシップ~
——立教大学...
立教大学特別授業