2019年度の研究・研究者紹介/書評研究・研究者紹介/書評
2020年(評者:立教大学異文化コミュニケーション学部准教授 石坂浩一)

2020年 岩波書店
3月6日の封切初日に映画〈Fukushima50〉を見た。東京電力福島第一原子力発電所の大事故の現場で踏みとどまり、爆発した原発の暴走を必死に抑えようとした人びとの物語である。その現場における苦闘はよく伝わってきた。リアルにできた作品だった。ただ、「事故は起こらない」といってきた原発で事故が発生してしまったこと、どのように危険な局面なのかということを、この人びとはわかっていた。一方で、必死だったのはこの人たちだけではなかっただろう。状況をよくわからないまま、数多くの人たちが避難させられた。そしていまだに住み慣れた地に帰ることができない人びとがいる。この映画が語っていないところも多い。
平コミのホームページで吉田千亜さんの前著『その後の福島-原発事故後を生きる人々』『ルポ 母子避難』を紹介したので、この本は書評の予定にはなかったが、手に取ってみて一気に読ませるだけのとても力のある著作だった。ここに紹介するゆえんである。
本書は月刊誌『世界』2019年3月号から9月号に連載された同名のルポをまとめ加筆修正したものである。また『世界』2020年4月号には、本書に登場する消防士の方の講演記録と著者の吉田さんの出版にあたっての思いが掲載された。東京電力福島第一の原発事故に関する本は少なからずあるが、消防士たちのことを記録した本は初めてだという。
地震発生で本書に登場する双葉郡消防本部の消防士たちは、地震発生以降、消火に、救急に、不眠不休で働き続けた。原発が大変なことになっているというのは、12日未明に救急搬送の要請があって原発に出動した消防隊員にはよく伝えられていなかった。免震重要棟に入る時、隊員はスクリーニング検査をされたが、この時には、なぜ検査をするのだろうと思ったのだという。しかし、まもなく消防士たちも防護服を身に着けることになる。外出していて戻った消防士は「そんなにヤバいのか」と思った。
12日には1号機が爆発した。そこからは、ポケット線量計が鳴り続けようとも、避難者や救急患者を助け、少ない水や食料に耐えつつ活動する消防士たちの修羅場に突入していく。消防士はもちろん、地元の人たちである。救助活動にあたりながら、自分の家族と連絡するすべもない消防士が少なくなかったし、助けに行くことなど、論外であった。ある消防士は、休む時間もなく活動していても、おまえらは防護服を着ていていいな、といわれた。若い消防士は、その言葉に「すいません」と繰り返し言うしかなかった。受け入れ先がなく、転々とした末にやっと病院に患者を搬送した消防士は、泣いた。
こうしている間にも、3号機が爆発した。原子炉の暴走を止めるため、冷却水注入をはかる作業に、原発から消防に対して応援要請が来た。サイト内の注水など、訓練でもしたことがないし、消火と救急という消防の任務からもはずれる。消防の指揮系統から言えば、消防長が部下に、行くべきかと問いかけることはない。しかし、この時に消防長は部下たちの意見を聞いた。多くが出動に反対した。ある消防士はこの時、人のいなくなった土地で今なお活動を続け、いままた冷却要請に葛藤しているわれわれのことを、国は知っているのだろうか、と思ったという。
しかし、16日早朝に4号機で火災が発生したとの通報で、消防士たちは原発へと出動した。消火は消防士の仕事なのである。そこに仕事があれば行かなければならないというのが、この人びとの律儀な精神であった。本書の帯に「きっと特攻隊はこうだったのだろう」という言葉が書かれているのは、この時のことである。ところが、4号機の火災はその後自然鎮火し、このことは消防に伝えられなかった。また、福島と東京電力本店とのやり取りでは、サイト内の高い線量を被ばくした人たちは、原発外部に出すことができないといって、消防士たちの扱いを議論していた記録があるが、それも消防本部には伝えられていなかった。ところが、サイト内の放射線量が急上昇しているとの知らせに、いったん出動した消防士たちはなすすべもなく撤退した。この間に、相当の被ばくをのがれることはできなかった。原発の職員たちは必死だったにちがいない。それでも、思わずにはいられない。東電の社員でもない消防士たちのことは、だれが責任をとるのか。著者は「災害発生から休む間もなく、もっとも危険な場所で活動し続けてきた消防士たちを、誰が守るべきだったのだろうか」と問いかけている。
『世界』に講演記録が出ている双葉消防本部元次長の渡邉敏行さんは、こういう思いを二度と、誰にもさせたくない、人間がコントロールできないものは作ってはいけない、と語ったことが本書に出てくる。また別の消防士は、大変だったねと声をかけられることもあるが、まだ終わっていない、と述べる。著者は最初にインタビューしたこの渡邉元次長の話があまりに印象的で、ほかの消防士から話を聞くことにし、予定になかった本書が出来上がったという。本書はこれまで注目されなかった人びとのとても大事な労苦を記録した、貴重な仕事に他ならない。「申し訳なさを一生背負わなくてはならない」という渡邉さんの言葉を著者は書き留めている。著者は自分こそ、彼に「背負わなくてはならない」と思わせてしまった人間の一人だと書く。
書くという仕事に就く者は、そこに出てくる人を大切にする気持ちがないと、誠実な仕事ができないのではないかと思う。これは迷いや葛藤を抱えつつ、壮絶な働きをした普通の人びとの記録であることが、本書から伝わってくるのではないだろうか。
著者は「バトンを渡す」という思いで書き続けてきたという。本書を読めば、問いかけは福島にいなかった人にも等しく投げかけられていることがひしひしと伝わってくる。そして、私たちの社会はこのままで大丈夫だろうかという思いにさせられるのではないだろうか。ひとりでも多くの人が、この「バトンを受け継ぐ」ように、願ってやまない。
異文化コミュニケーション学部 石坂浩一
2019年(評者:立教大学異文化コミュニケーション学部准教授 石坂浩一)
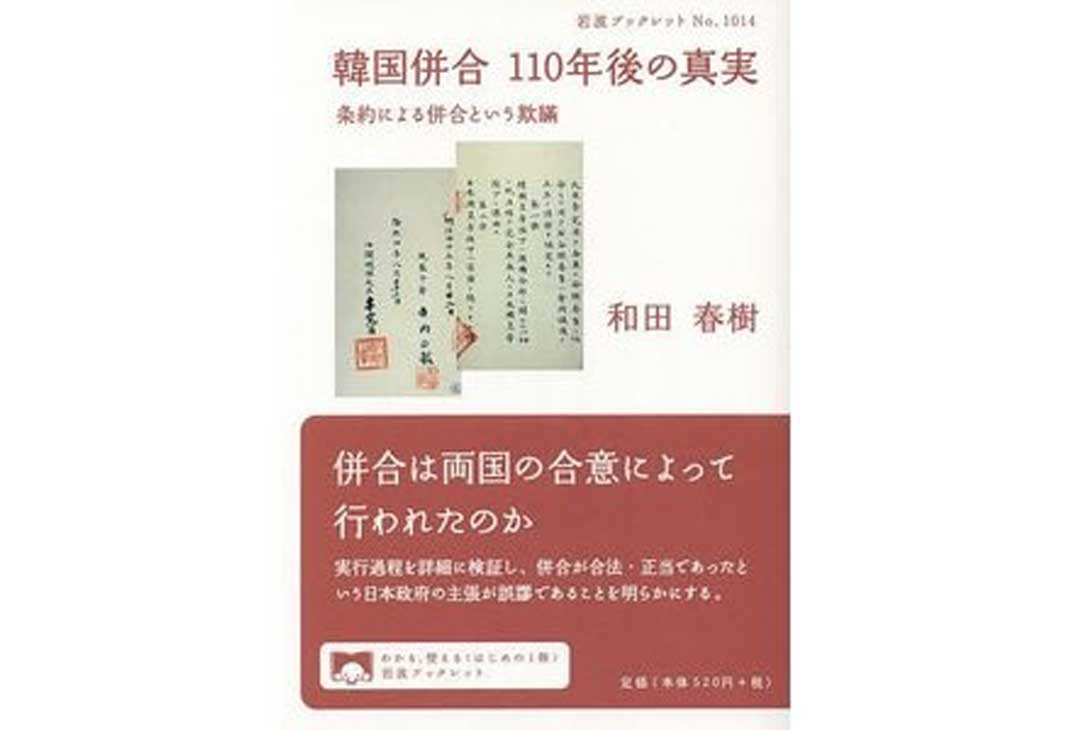
2019年12月 岩波ブックレット
昨今、李栄薫(イ・ヨンフン)編『反日種族主義』(日本語版は文藝春秋社)が日本でベストセラーとなり販売部数が40万部を超えたという。ソウル大学教授をはじめ韓国のそうそうたる研究者が執筆したというこの本だが、その内容は、はなはだ心もとない限りである。論者の意図に沿わない主張を「ウソ」「ウソつき」と退けるだけのこの本が、著者として名前を連ねた人たちにとって、後々までの恥になるのではないかと心配してしまう。
議論は資料(史料)をもって論理的に進められるべきことは言うまでもない。韓国併合についての研究の成果が、入手しやすいブックレットの形であらわされた和田春樹『韓国併合 110年後の真実』は、たくさんの本があふれているためか、紹介される機会が多くないが、重要な本である。出発点は、韓国併合条約に至る過程の実態がどのようなものだったのかという、わかっていそうでいて、よく解明されていない史実にあった。
日本政府は1965年の日韓国交正常化において、1910年の併合条約や関連した合意は、韓国側に対する「威嚇や脅迫」なしに合法的に行われたと主張し、今日までその見解を崩していない。1990年代末には明治大学の海野福寿先生が『韓国併合』(1995、岩波書店)、『韓国併合史の研究』(2000、岩波書店)などで併合条約についての実証的研究を行ない、韓国の併合は不当だが、当時の帝国主義時代にあっては合法といわざるを得ないと述べた。だが、これに対しソウル大学のイ・テジン(李泰鎮)教授が条約締結の手続き上も条約形式上も問題があり、合法とは言えないと主張、『世界』などで論争が行なわれた。
その後、2010年に韓国併合100周年を迎えて、日韓の歴史研究者は併合とその条約が「不義不当」であるとの共同声明を発表、あらためて併合過程についての実証的研究に取り組んでいた。和田春樹先生の本書はその成果の一端である。
日本は日露戦争が1905年9月に終了したのちも韓国(この時期、朝鮮王朝は大韓帝国と国号を変えていた)の軍事占領を続け、この年11月には第2次日韓協約(いわゆる保護条約)を強要した。これにより大韓帝国は外交権を失った。日本政府内では、すでに保護国となった韓国を、詔勅を出すことで併合するか、条約を締結することで併合するかの選択肢があったが、後者を選択することになる。韓国内外の反発を抑えるために、韓国側が、形式上は受け入れた形での条約締結が望ましいと考えたのだった。
しかし、条約案を作ったのは日本の陸軍大臣を兼務していた寺内正毅統監であった。統監は日本政府に任命され韓国を代表する役割である。日本国の全権大使でも何でもない。示された条約案を韓国側で受け入れたのは李完用首相ら大臣であった。寺内の下で働く人物である。李完用首相は純宗皇帝の全権委任状を受け、条約に署名するに至る。条約とは本来国家間の権限を持った代表同士が署名して締結すべきものだが、併合条約はこうしたルールに反するものだった。もちろん、この時期には朝鮮半島全体が日本軍の支配下に置かれていたのであった。著者は「併合条約の調印とは、対等な条約を結ぶ資格を持たない者同士、支配国の代表者とその指揮監督を受ける被支配国の役人が演じた条約調印の演劇、芝居」だと指摘している。
歴史に基づいた議論とは、このような研究の基盤のうえに立ったものであるはずだ。昨今、日本ではわかりやすいものが良しとされてしまう風潮があるが、わかりやすそうでも事実でなければ、意味はない。こうした見方が広がれば、後世へ火種を残すばかりである。朝鮮を植民地化する過程について、事実の検証をきちんと行なうためには、このブックレットのような冷静な研究が社会的に共有されることが欠かせないのではないだろうか。
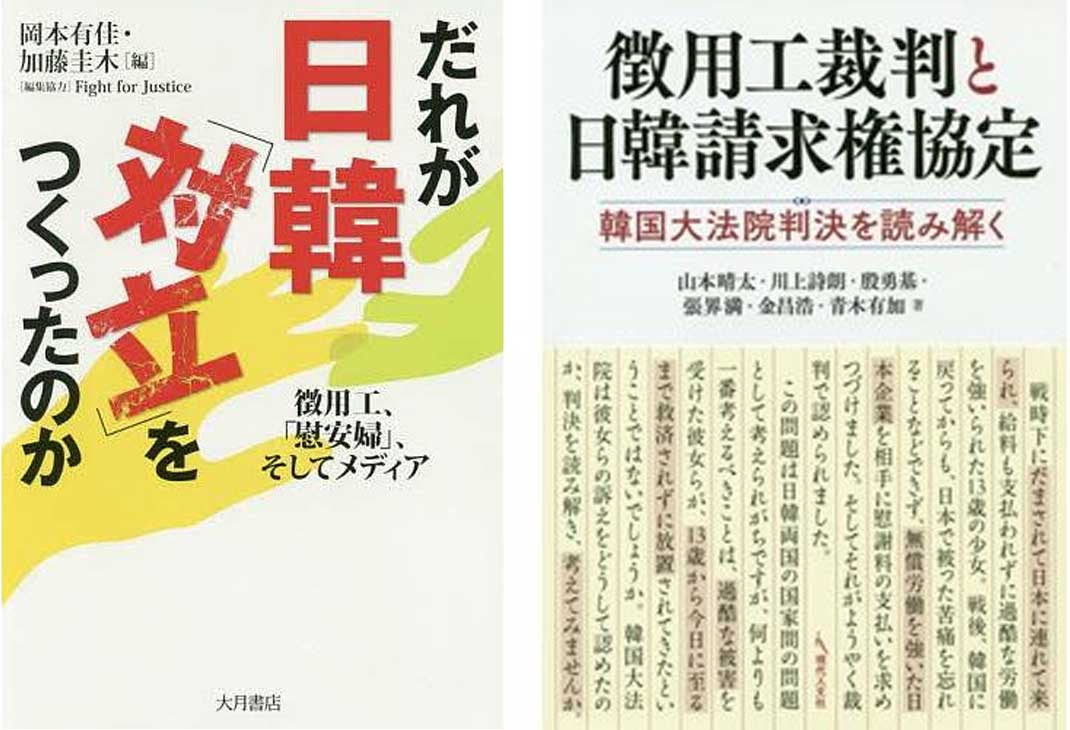
なお、昨年来の日韓の葛藤に対し冷静な議論を促すため、ほかにも注目すべき論著が出されている。わかりやすいものとして岡本有佳・加藤圭木編『だれが日韓「対立」を作ったのか——徴用工、 「慰安婦」、そしてメディア』(大月書店)、いわゆる徴用工問題について日本政府の立場が意図的に変えられたことを論証する山本晴太ほか『徴用工裁判と日韓請求権協定——韓国大法院判決を読み解く』(現代人文社)などをお勧めしたい。
異文化コミュニケーション学部 石坂浩一
2019年(評者:立教大学異文化コミュニケーション学部准教授 石坂浩一)
今、事実を拡散する責任
8月27日の記者会見において、河野太郎外務大臣は外国人記者から、日韓請求権協定をめぐり韓国政府が日本は歴史への理解が足りないと指摘しているが、どう思うかと問われた。すると、河野外相は、韓国政府が歴史を書き換えたいと考えているならば、そんなことはできないと知る必要がある、と答えたという。(『毎日新聞』2019年8月28日)
そもそも、全然話がかみ合っていない。それだけではなく、その認識には驚かされる。日韓に関わる歴史問題というとき、それはいうまでもなく植民地支配の問題であるし、すこし広いスパンで見れば1875年の江華島事件に端を発する不平等条約の強要(翌年に結ばれた日朝修好条規)から始まる近代史である。しかし、日本を代表して外交を担当する河野外相にとっては、植民地支配やそこに至る歴史はなかったのだ。河野外相はこの席で、日韓条約、請求権協定の約束を守れという話を繰り返したという。この人には、日韓条約からしか記憶がないのだろうか。あるいは、意図的に近代の歴史を無視したのだろうか。日韓条約や諸協定には「謝罪」や「遺憾」はおろか、「植民地」という言葉さえ使われていないことの意味も、外相の発想の中にはないにちがいない。かつて、「歴史を書き換えることはできない」という時、それは侵略や植民地化、戦争の歴史を指して、侵略された側が語ったことであった。それが、21世紀の今日では、一種の開き直りの言葉として使われるようになってしまった。この報道を見て、あらためて関東大震災の朝鮮人虐殺について考えさせられた。
本書の著者加藤直樹さんは前著『九月、東京の路上で 1923年関東大震災の残響』(ころから、2014年)で関東大震災の朝鮮人虐殺について、わかりやすく、かつ事実に基づいた叙述で私たち歴史研究者にインパクトを与えた。この本は、日本社会でも静かな関心を呼び、広く読まれたようで、あちこちで紹介された。関東大震災において多数の朝鮮人が虐殺され、また中国人や、朝鮮人とまちがわれて殺害された日本人も犠牲となったことは、否定しようもない歴史的事実に他ならない。しかし、いま日本社会ではどのようにとらえられているだろうか。
著者は前書きにこのように記す。
近年、インターネット上で「朝鮮人虐殺はなかった」「朝鮮人は本当に暴動を起こした」といった主張が拡がるようになった。このままでは、この事件から現代の私たちが学ぶべき教訓——民族差別の恐ろしさや災害時の差別デマへの警戒、行政の責任の重さ——が打ち捨てられることになってしまう。
本書は、第1章でネット上に拡散している朝鮮人虐殺否定論がどのようにまちがっているかを説明し、第2章で虐殺否定論が使うトリックを明らかにし、第3章では虐殺否定論が現実社会にどれほど浸透しているかをあげて、それに対抗すべき必要性を確認する。
関東大震災は天災であり、だれも予測することができなかった。まして、日本にいた朝鮮人たちは今ほど日本語ができる人たちもいなかったし、地震には慣れていないため経験したこともないような大地の揺れと、襲ってくる火災などに、慌てふためくだけであったろう。その人びとが、井戸に投じる毒を準備していたり、暴動を準備していたというのは、常識で考えても無理のあることだ。だからこそ、関東大震災における朝鮮人虐殺は、無視されることこそあれ、否定はされてこなかったのである。
ところが、新しくもない新聞記事に依拠し、歴史的文脈を無視して勝手に「朝鮮人の暴動」があったかのごとく主張する人びとが現れた。そして、現在インターネット上では「暴動」があったのが事実とする、歴史に反する言説があふれかえっている。その事実に即さない主張は、朝鮮人虐殺がなかったという、中学校の教科書の叙述にも反する言説へと「発展」しているのである。
著者の加藤直樹さんは、「暴動」があったといい、「虐殺はなかった」と主張したい人びとの言い分をひとつひとつ検証し、そのウソを明らかにする。詳しくは本をお読みいただきたいが、「虐殺否定論とは認識の誤りではなく、人をだます目的で仕掛けられた“トリック”なのだ。」という前書きの一節は本書の狙いを端的に表現している。
この本に強い印象を受けるのは、わかりやすく、インターネット上にあるような書き方を使いながら、なおかつ基本資料を丹念に洗い出し、先行研究をきちんと踏まえて書かれていることである。一般に大学で研究に従事する者は、わかりやすい叙述、あるいは明快な書きぶりについて、あまり得意ではない。だが、研究者が自分の研究成果を進んで広く拡散しない限り、その成果は認識されずに終わってしまう。加藤さんの本を読むと、大学の研究者の姿勢が問い直されていることがわかる。
そもそも、全然話がかみ合っていない。それだけではなく、その認識には驚かされる。日韓に関わる歴史問題というとき、それはいうまでもなく植民地支配の問題であるし、すこし広いスパンで見れば1875年の江華島事件に端を発する不平等条約の強要(翌年に結ばれた日朝修好条規)から始まる近代史である。しかし、日本を代表して外交を担当する河野外相にとっては、植民地支配やそこに至る歴史はなかったのだ。河野外相はこの席で、日韓条約、請求権協定の約束を守れという話を繰り返したという。この人には、日韓条約からしか記憶がないのだろうか。あるいは、意図的に近代の歴史を無視したのだろうか。日韓条約や諸協定には「謝罪」や「遺憾」はおろか、「植民地」という言葉さえ使われていないことの意味も、外相の発想の中にはないにちがいない。かつて、「歴史を書き換えることはできない」という時、それは侵略や植民地化、戦争の歴史を指して、侵略された側が語ったことであった。それが、21世紀の今日では、一種の開き直りの言葉として使われるようになってしまった。この報道を見て、あらためて関東大震災の朝鮮人虐殺について考えさせられた。
本書の著者加藤直樹さんは前著『九月、東京の路上で 1923年関東大震災の残響』(ころから、2014年)で関東大震災の朝鮮人虐殺について、わかりやすく、かつ事実に基づいた叙述で私たち歴史研究者にインパクトを与えた。この本は、日本社会でも静かな関心を呼び、広く読まれたようで、あちこちで紹介された。関東大震災において多数の朝鮮人が虐殺され、また中国人や、朝鮮人とまちがわれて殺害された日本人も犠牲となったことは、否定しようもない歴史的事実に他ならない。しかし、いま日本社会ではどのようにとらえられているだろうか。
著者は前書きにこのように記す。
近年、インターネット上で「朝鮮人虐殺はなかった」「朝鮮人は本当に暴動を起こした」といった主張が拡がるようになった。このままでは、この事件から現代の私たちが学ぶべき教訓——民族差別の恐ろしさや災害時の差別デマへの警戒、行政の責任の重さ——が打ち捨てられることになってしまう。
本書は、第1章でネット上に拡散している朝鮮人虐殺否定論がどのようにまちがっているかを説明し、第2章で虐殺否定論が使うトリックを明らかにし、第3章では虐殺否定論が現実社会にどれほど浸透しているかをあげて、それに対抗すべき必要性を確認する。
関東大震災は天災であり、だれも予測することができなかった。まして、日本にいた朝鮮人たちは今ほど日本語ができる人たちもいなかったし、地震には慣れていないため経験したこともないような大地の揺れと、襲ってくる火災などに、慌てふためくだけであったろう。その人びとが、井戸に投じる毒を準備していたり、暴動を準備していたというのは、常識で考えても無理のあることだ。だからこそ、関東大震災における朝鮮人虐殺は、無視されることこそあれ、否定はされてこなかったのである。
ところが、新しくもない新聞記事に依拠し、歴史的文脈を無視して勝手に「朝鮮人の暴動」があったかのごとく主張する人びとが現れた。そして、現在インターネット上では「暴動」があったのが事実とする、歴史に反する言説があふれかえっている。その事実に即さない主張は、朝鮮人虐殺がなかったという、中学校の教科書の叙述にも反する言説へと「発展」しているのである。
著者の加藤直樹さんは、「暴動」があったといい、「虐殺はなかった」と主張したい人びとの言い分をひとつひとつ検証し、そのウソを明らかにする。詳しくは本をお読みいただきたいが、「虐殺否定論とは認識の誤りではなく、人をだます目的で仕掛けられた“トリック”なのだ。」という前書きの一節は本書の狙いを端的に表現している。
この本に強い印象を受けるのは、わかりやすく、インターネット上にあるような書き方を使いながら、なおかつ基本資料を丹念に洗い出し、先行研究をきちんと踏まえて書かれていることである。一般に大学で研究に従事する者は、わかりやすい叙述、あるいは明快な書きぶりについて、あまり得意ではない。だが、研究者が自分の研究成果を進んで広く拡散しない限り、その成果は認識されずに終わってしまう。加藤さんの本を読むと、大学の研究者の姿勢が問い直されていることがわかる。
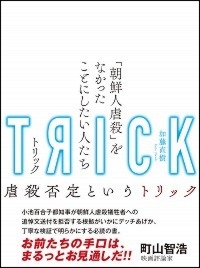
関東大震災での虐殺について、一般に民衆が朝鮮人を虐殺したことが強調されるが、軍隊や警察が虐殺を実行している点は軽く見られがちだ。国家や軍が誤認情報を流布した責任、軍や警察がみずから虐殺を行なった責任は、まだ十分問われていない。姜徳相・琴秉洞編『現代史資料6 関東大震災と朝鮮人』(1963、みすず書房)に朝鮮人虐殺をめぐる基本資料が収められており、官憲資料から軍や警察が「暴動」の誤認情報を流布したことが読み取れる。また、山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺とその後』(2011、創史社)に研究の現段階が詳しく述べられているので、ご参照いただきたい。
当然のことだが、虐殺された朝鮮人ひとりひとりに家族があり、生活があったはずだ。この人びとの死について、誰が責任を取るのか。この問題は日本と南北朝鮮の間で協議されておらず、未解決の課題に他ならない。本来は、こうして無念の死を遂げた朝鮮人ひとりひとりについて、調べ上げ追悼する事業がなされるべきなのに、日本社会の風潮が逆行しているのは、はなはだ残念である。関東大震災の朝鮮人虐殺について、一層の調査研究を進め、その事実を拡散していく社会的責任を私たち研究者は背負っているのである。
当然のことだが、虐殺された朝鮮人ひとりひとりに家族があり、生活があったはずだ。この人びとの死について、誰が責任を取るのか。この問題は日本と南北朝鮮の間で協議されておらず、未解決の課題に他ならない。本来は、こうして無念の死を遂げた朝鮮人ひとりひとりについて、調べ上げ追悼する事業がなされるべきなのに、日本社会の風潮が逆行しているのは、はなはだ残念である。関東大震災の朝鮮人虐殺について、一層の調査研究を進め、その事実を拡散していく社会的責任を私たち研究者は背負っているのである。
異文化コミュニケーション学部 石坂浩一
はじめまして。2019年3月に立教大学社会学研究科後期課程を修了し、今年度5月に平和・コミュニティ研究機構特任研究員にご承認いただきました三浦優子です。
主指導教員である社会学部の水上徹男先生と副指導教員の木村自先生のご指導のもと「日本人エクスパトリエイト・コミュニティに関する社会学的実証研究—駐在員女性配偶者の日常生活実践の事例—」というタイトルで博士論文を執筆しました。論文では、トランスナショナルな社会空間に形成される日本人エクスパトリエイト・コミュニティの特徴を明らかにするにあたり、ドイツ・デュッセルドルフに暮らす海外駐在員配偶者の日常生活実践に焦点を当てました。なお、論文においては、駐在員中心のコミュニティをエクスパトリエイト・コミュニティとして捉えました。
主指導教員である社会学部の水上徹男先生と副指導教員の木村自先生のご指導のもと「日本人エクスパトリエイト・コミュニティに関する社会学的実証研究—駐在員女性配偶者の日常生活実践の事例—」というタイトルで博士論文を執筆しました。論文では、トランスナショナルな社会空間に形成される日本人エクスパトリエイト・コミュニティの特徴を明らかにするにあたり、ドイツ・デュッセルドルフに暮らす海外駐在員配偶者の日常生活実践に焦点を当てました。なお、論文においては、駐在員中心のコミュニティをエクスパトリエイト・コミュニティとして捉えました。

中心市街地の日本人通り(2019年4月撮影)
わたしが海外における日本人エクスパトリエイト・コミュニティやそのコミュニティに暮らす駐在員配偶者に興味を持ったきっかけは、自身が駐在員の夫に帯同してニューヨークに5年、デュッセルドルフに10年暮らしたことにあります。現地で他の駐在員配偶者とつながる中で女性たちが生活の中でさまざまな思いを抱き暮らしていること、そして上記2都市の駐在経験から海外の日本人社会が国や都市によって全く異なることを実感しました。帰国して数年経ち、10年滞在したデュッセルドルフの日本人社会をさらに掘り下げ、その中で暮らす駐在員配偶者たちの生活世界を詳しくみていきたいと思いました。
研究の対象地となるデュッセルドルフですが、当市はドイツ国内16州のひとつであるノルトライン・ヴェストファーレン州(以下NRW州と記す)の州都で、人口は642,304人でそのうち日本人は5,982人(Landeshauptstadt Duesseldforf 2018)です。全体の人口から見れば、邦人は1%にも満たず、ロスアンジェルスやニューヨークなど他都市に比べると人数的には多いとは言えませんが、日系企業が多く進出し、日本人駐在員が中心となった日本人社会があります。また、ある一定の地域に日本人が集住して暮らすという特徴もあります。NRW州の日系企業のほとんどが入会するデュッセルドルフ日本商工会議所のデータによると2019年1月の時点で、当商工会議所の正社員は302社を越え、そのうち製造業関係が207社で全体の約70%を占めます。デュッセルドルフへの日系企業進出の背景には、ヨーロッパの中心に位置するという地理的優位性、会計士や弁護士など企業を日本語でサポートする体制並びに日本人向け教育機関や病院、日本食料品店など生活インフラ構造が整っていることがあげられます(デュッセルドルフ日本商工会議所)。
私たち家族は、デュッセルドルフに2000年から2010年まで10年暮らしましたが、渡独直後、驚いたのは、海外に居ながらも、買い物は日本食スーパー、友だちも日本人駐在員ばかり、習い事も日本人向けに用意されたもので、子どもたちは日本人学校や進学塾に通い、日本での生活を再生産したような暮らしをしている駐在員配偶者たちを目の当たりにしたことです。私たち一家は、現地においては現地のやり方に従うという家族の方針であったので、渡独時5歳だった次女は現地の幼稚園、そして現地校と進みました。小学校3年生の長女は、現地に日本人学校があるのならそこに行きたいという本人の希望を尊重し、デュッセルドルフの日本人学校に編入しました。しかし、現地の生活も3年経った頃、長女は海外に住みながらもドイツ語も英語もできない自分に疑問を感じたのか、6年生からデュッセルドルフのインターナショナルスクールに転校しました。
研究の対象地となるデュッセルドルフですが、当市はドイツ国内16州のひとつであるノルトライン・ヴェストファーレン州(以下NRW州と記す)の州都で、人口は642,304人でそのうち日本人は5,982人(Landeshauptstadt Duesseldforf 2018)です。全体の人口から見れば、邦人は1%にも満たず、ロスアンジェルスやニューヨークなど他都市に比べると人数的には多いとは言えませんが、日系企業が多く進出し、日本人駐在員が中心となった日本人社会があります。また、ある一定の地域に日本人が集住して暮らすという特徴もあります。NRW州の日系企業のほとんどが入会するデュッセルドルフ日本商工会議所のデータによると2019年1月の時点で、当商工会議所の正社員は302社を越え、そのうち製造業関係が207社で全体の約70%を占めます。デュッセルドルフへの日系企業進出の背景には、ヨーロッパの中心に位置するという地理的優位性、会計士や弁護士など企業を日本語でサポートする体制並びに日本人向け教育機関や病院、日本食料品店など生活インフラ構造が整っていることがあげられます(デュッセルドルフ日本商工会議所)。
私たち家族は、デュッセルドルフに2000年から2010年まで10年暮らしましたが、渡独直後、驚いたのは、海外に居ながらも、買い物は日本食スーパー、友だちも日本人駐在員ばかり、習い事も日本人向けに用意されたもので、子どもたちは日本人学校や進学塾に通い、日本での生活を再生産したような暮らしをしている駐在員配偶者たちを目の当たりにしたことです。私たち一家は、現地においては現地のやり方に従うという家族の方針であったので、渡独時5歳だった次女は現地の幼稚園、そして現地校と進みました。小学校3年生の長女は、現地に日本人学校があるのならそこに行きたいという本人の希望を尊重し、デュッセルドルフの日本人学校に編入しました。しかし、現地の生活も3年経った頃、長女は海外に住みながらもドイツ語も英語もできない自分に疑問を感じたのか、6年生からデュッセルドルフのインターナショナルスクールに転校しました。

日本人学校近くの日本食スーパー
研究においてデュッセルドルフを調査対象地にしたのは、子どもたちが、日本人学校以外に現地校、日本語補習校、インターナショナルスクールに通ったことで日本人駐在員配偶者以外の知り合いのネットワークが一挙に広がり、フィールド調査にアクセスしやすかったこともあります。駐在中に、現地の永住日本人、ドイツ人と国際結婚した日本人、ドイツ人や諸外国の人々とつながっていきました。そして、日本人駐在員配偶者の中にも日本人だけの狭い社会から飛び出し、積極的に現地の人々と接点を求めようとする女性、現地の市民大学で一生懸命ドイツ語を勉強する女性、私たち家族のように現地の小学校に子どもを入れている女性の存在を知りました。また現地では就労ビザや夫の会社の方針で仕事がしたくてもできず悶々とした気もちで生活を送る女性、日本人社会の中で他の駐在員配偶者たちに違和感を感じながらもわだかまりなく過ごそうとする女性、ドイツの生活を運命と受け止め静かに過ごせる生活に感謝しながら日々を送る女性など様々な思いをもつ女性たちと出会いました。渡独直後は、自分のなかで、「駐在員配偶者」たちは皆、日本人同士でつながり、現地と交わらないと単純に一括りに捉えていましたが、個々に話をしてみるとそれぞれが肯定感あるいは葛藤や危機感など様々な思いを抱きながら暮らしていることが分かりました。
10年のデュッセルドルフ生活を終え、日本に帰国しますが、自分が日本人でありながら、日本の社会と全く接点がないという現実に直面します。一体これから自分はどのように人生を歩んでいったらいいのかと考える毎日でした。そのような時に、数人のデュッセルドルフから帰国した女性たちと会う機会があり、皆、駐在生活を帰国後の自分の生き方にどのようにつなげていくのかを模索していることを知りました。女性たちの中には、あんなに「駐在員の妻」として頑張ってやってきたのに日本に帰ったら、全く今までの努力が報われないと嘆いている女性、数回の海外駐在経験のある女性は、駐在生活はそれぞれ楽しかったが、自分の人生がぶつぶつ切れて中断され、すべて中途半端で終わってしまうと感じている女性もいました。
帰国して3年程経ち、自分の今後の生き方を考える中で今一度、駐在員配偶者の世界をさらに掘り下げてみようと思いたち、立教大学の異文化コミュニケーション独立研究科に進みました。修士論文では諸外国に暮らした日本人駐在員女性たちにライフストーリーインタビューを行い、「海外駐在生活が女性たちの家族観に与える影響」についてまとめました。しかし、女性たちの生活世界を見ていくにあたり、ジェンダーやさらに大きな社会構造の枠の中でとらえる必要性を感じ、社会学研究科の博士後期課程で研究を続けることにしました。
博士論文では、調査対象地を10年暮らしたデュッセルドルフに絞り、戦後から形成されたデュッセルドルフの日本人社会の歴史、デュッセルドルフ日本人コミュニティや他都市の海外日本人社会についての先行研究や文献を整理しまとめました。また、2015年から2018年まで7回現地を訪れ、現地の日本人学校、日本商工会議所、日本クラブなどの日本人関連機関や団体などへの聞き取り調査や、当市に暮らす駐在員配偶者たちにインタビューを行いました。さらにデュッセルドルフから帰国した駐在員配偶者たちにもインタビューを依頼しました。
博論執筆を通して、駐在員配偶者が駐在員生活の中でかかえる両義性、駐在生活において強化された性別役割分業などのジェンダー問題、海外における日本人コミュニティの社会構造などにおける様々な課題が浮き彫りになりました。経済や社会のグローバル化が進む中で、国を越えたトランスナショナルな社会空間にあるエクスパトリエイト・コミュニティも変容を続け、コミュニティに暮らす駐在員配偶者の意識や価値観も変わりつつあると考えられます。しかしながら、女性たちはいまだに良い妻・良い母であることへの期待に添うように生活実践を試み、葛藤を抱えたり、自分の生き方に疑問を感じながら暮らしています。このように交錯する思いで暮らす駐在員配偶者の生活世界は、いままで夫の背後に隠れ不可視化されてきました。
今後は、他の国や都市における日本人社会、ジェンダー問題、そして変容する経済や社会も視野に入れながら、海外で暮らす駐在員配偶者や家族が自分らしく生きることのできるコミュニティの在り方を考え続けていきたく思っています。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
10年のデュッセルドルフ生活を終え、日本に帰国しますが、自分が日本人でありながら、日本の社会と全く接点がないという現実に直面します。一体これから自分はどのように人生を歩んでいったらいいのかと考える毎日でした。そのような時に、数人のデュッセルドルフから帰国した女性たちと会う機会があり、皆、駐在生活を帰国後の自分の生き方にどのようにつなげていくのかを模索していることを知りました。女性たちの中には、あんなに「駐在員の妻」として頑張ってやってきたのに日本に帰ったら、全く今までの努力が報われないと嘆いている女性、数回の海外駐在経験のある女性は、駐在生活はそれぞれ楽しかったが、自分の人生がぶつぶつ切れて中断され、すべて中途半端で終わってしまうと感じている女性もいました。
帰国して3年程経ち、自分の今後の生き方を考える中で今一度、駐在員配偶者の世界をさらに掘り下げてみようと思いたち、立教大学の異文化コミュニケーション独立研究科に進みました。修士論文では諸外国に暮らした日本人駐在員女性たちにライフストーリーインタビューを行い、「海外駐在生活が女性たちの家族観に与える影響」についてまとめました。しかし、女性たちの生活世界を見ていくにあたり、ジェンダーやさらに大きな社会構造の枠の中でとらえる必要性を感じ、社会学研究科の博士後期課程で研究を続けることにしました。
博士論文では、調査対象地を10年暮らしたデュッセルドルフに絞り、戦後から形成されたデュッセルドルフの日本人社会の歴史、デュッセルドルフ日本人コミュニティや他都市の海外日本人社会についての先行研究や文献を整理しまとめました。また、2015年から2018年まで7回現地を訪れ、現地の日本人学校、日本商工会議所、日本クラブなどの日本人関連機関や団体などへの聞き取り調査や、当市に暮らす駐在員配偶者たちにインタビューを行いました。さらにデュッセルドルフから帰国した駐在員配偶者たちにもインタビューを依頼しました。
博論執筆を通して、駐在員配偶者が駐在員生活の中でかかえる両義性、駐在生活において強化された性別役割分業などのジェンダー問題、海外における日本人コミュニティの社会構造などにおける様々な課題が浮き彫りになりました。経済や社会のグローバル化が進む中で、国を越えたトランスナショナルな社会空間にあるエクスパトリエイト・コミュニティも変容を続け、コミュニティに暮らす駐在員配偶者の意識や価値観も変わりつつあると考えられます。しかしながら、女性たちはいまだに良い妻・良い母であることへの期待に添うように生活実践を試み、葛藤を抱えたり、自分の生き方に疑問を感じながら暮らしています。このように交錯する思いで暮らす駐在員配偶者の生活世界は、いままで夫の背後に隠れ不可視化されてきました。
今後は、他の国や都市における日本人社会、ジェンダー問題、そして変容する経済や社会も視野に入れながら、海外で暮らす駐在員配偶者や家族が自分らしく生きることのできるコミュニティの在り方を考え続けていきたく思っています。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
『植民地朝鮮における日本の同化政策1910〜1945』
マーク・カプリオ
本書『植民地朝鮮における日本の同化政策1910〜1945』で、私は朝鮮における日本の同化政策を、その起源から日本の敗戦による終焉まであとづけようと試みた。日本の同化思想の起源はどこにあるのか?日本人はその政策をいかに国家形成過程に位置づけようとしたのか、明治維新以後、日本国家に所属させた人びとにどのように適用しようとしたのか?35年以上にわたる植民地支配の間、この政策はどのような展開をしたのか?植民地支配を受けた朝鮮人はいかにこの政策に反応したのか?本書は日本の朝鮮植民地支配を、より広大なスケールで、またさまざまなレベルの強制力をともなった広範な国際的な動きの一部として描き出そうとしている。
各章の内容は以下の通りである。
序論:ここでは本書の内容を概観している。私はここで3つの形態の植民地拡張を提示した。第1の形態は「内国植民地政策」の最も強力な国民形成政策であり、支配的な文化を核にして人びとを国民に統合しようとする。第2の形態としては、それほど強力ではないが、統合された国家が「周辺植民地政策」によって隣接する領土を付属することがある。その場合、同化は政策として一般的に宣言されることはあっても完全におこなわれることはない。最後に、地理的に遠く、住民が人種的にもかけ離れている領土を、その自然資源や人的資源を利用するために、労せずして従属せしめる「国外植民地政策」がある。
第1章:西洋諸国が上述の3つの形態で植民地を拡大した近代ではありませんかの歴史をあとづける。とくに岩倉使節団 (1871-73) が経験した植民地支配の実態に注目している。使節団は普仏戦争でフランスが破れた後の植民地拡大を目撃した。この影響は、日本が台湾 (1895年)、朝鮮 (1910) を獲得して世界の膨張主義をくり返すことになった 1910年まで続いている。同化政策はヨーロッパにおいて、その意図と結果の齟齬を生み出していたが、そうした歴史はどの程度、同時代の日本の決定に影響を及ぼしたであろうか。
第2章:日本の教育と同化政策実施の歴史を概観する。日本は江戸時代、18世紀後半にロシアの探検家たちが蝦夷までやって来たのに対抗して、蝦夷に短期間、同化政策を適用したことがあった。この同化政策はロシアが撤退すると間もなく終わった。しかしながら、明治維新後の新政府は江戸時代の約270の藩をより緊密に統合しようとして強力な中央集権化をおこなった。「同化」という言葉はここでいう政策にはふさわしくないかも知れないが、明治国家の政策は基本的に、かつては藩に対するアイデンティティを保持していた日本列島全体の人びとを同化しようとしたのである。蝦夷すなわち北海道と琉球すなわち沖縄を獲得したことによって、私が「周辺植民地政策」と呼ぶ政策を採用したのである。そこでの経験は日本政府が明治時代後期に台湾を獲得した際に適用した政策と共通の特徴を有している。
第3−5章:ここでは植民地政策がどのように朝鮮半島に適用されたかを考察する。第3章は1919年3月1日の独立運動の時期を扱っている。第4章はこの運動が日本人の認識をどのように変えたのかに注目している。このころから植民地政策にたいする支持とともに、(1800年代前後からのヨーロッパと同様に)同化は劣った人びととともに進めるには、不可能ではないにしても困難な政策であるという否定的な見方が広がった。
第5章は1930年代から40年代を考察している。この時期、日本がアジアにおける戦争を遂行するために朝鮮のより広範な協力を必要とした戦時期の状況のゆえに、同化についての確信がよみがえったと思われる。この時期をつうじて、日本人男性が日本軍に入隊するために朝鮮半島における仕事から離れたために、朝鮮人の割合は拡大した。ここまでの3つの章を通じて、日本の教育政策が最も注目される。というのも、もし同化が本気になって実行されたならば、同化される人びとは教育が自分たちを本国の人びとすなわち日本人の水準に引き上げると考えたからである。朝鮮(だけではなくアイヌや琉球、台湾の人びとに対しても)に導入された教育が低い水準のものであったことは、第1章で論じたように、ヨーロッパや米国など他の周辺植民地政策においてもよく見られたことであった。
第6章:この最終章では日本の同化政策にたいする朝鮮人の反応を考察している。まず、三一独立運動後の改革として導入された朝鮮語メディアの反日の声とそれらがどのように同化政策を批判しているかを論じ、続いて日本の植民地支配を受入れた「親日派」の声を紹介している。彼らは同化政策にどのような欠点を見出しているだろうか。日本の植民地支配当局にどのような示唆を与えているであろうか。
結論:この最終的な議論で、なぜ日本人は同化政策をさらに進めることができなかったかを論じている。なぜ、日本はヨーロッパで同化政策を行なった諸国が直面した、同化政策の論理と政策との間に存在する矛盾を克服することができなかったのか。日本の植民地支配の歴史は、たとえばアルジェリアにおけるフランスのそれよりも短かった。朝鮮における同化政策の最終的な結果を考えた日本人は、そのためには何世代も、50年、100年もかかるだろうと予想した。朝鮮総督府は前向きに進んでいることを示していただろうか。それとも、朝鮮人の戦時における社会的な進歩がさらに進行したら、日本人は戦争の終結後も朝鮮半島を保持し続けることができただろうか。結論としては、本研究はそのようにはならなかっただろうことを示している。
本学異文化コミュニケーション学部教授
本書『植民地朝鮮における日本の同化政策1910〜1945』で、私は朝鮮における日本の同化政策を、その起源から日本の敗戦による終焉まであとづけようと試みた。日本の同化思想の起源はどこにあるのか?日本人はその政策をいかに国家形成過程に位置づけようとしたのか、明治維新以後、日本国家に所属させた人びとにどのように適用しようとしたのか?35年以上にわたる植民地支配の間、この政策はどのような展開をしたのか?植民地支配を受けた朝鮮人はいかにこの政策に反応したのか?本書は日本の朝鮮植民地支配を、より広大なスケールで、またさまざまなレベルの強制力をともなった広範な国際的な動きの一部として描き出そうとしている。
各章の内容は以下の通りである。
序論:ここでは本書の内容を概観している。私はここで3つの形態の植民地拡張を提示した。第1の形態は「内国植民地政策」の最も強力な国民形成政策であり、支配的な文化を核にして人びとを国民に統合しようとする。第2の形態としては、それほど強力ではないが、統合された国家が「周辺植民地政策」によって隣接する領土を付属することがある。その場合、同化は政策として一般的に宣言されることはあっても完全におこなわれることはない。最後に、地理的に遠く、住民が人種的にもかけ離れている領土を、その自然資源や人的資源を利用するために、労せずして従属せしめる「国外植民地政策」がある。
第1章:西洋諸国が上述の3つの形態で植民地を拡大した近代ではありませんかの歴史をあとづける。とくに岩倉使節団 (1871-73) が経験した植民地支配の実態に注目している。使節団は普仏戦争でフランスが破れた後の植民地拡大を目撃した。この影響は、日本が台湾 (1895年)、朝鮮 (1910) を獲得して世界の膨張主義をくり返すことになった 1910年まで続いている。同化政策はヨーロッパにおいて、その意図と結果の齟齬を生み出していたが、そうした歴史はどの程度、同時代の日本の決定に影響を及ぼしたであろうか。
第2章:日本の教育と同化政策実施の歴史を概観する。日本は江戸時代、18世紀後半にロシアの探検家たちが蝦夷までやって来たのに対抗して、蝦夷に短期間、同化政策を適用したことがあった。この同化政策はロシアが撤退すると間もなく終わった。しかしながら、明治維新後の新政府は江戸時代の約270の藩をより緊密に統合しようとして強力な中央集権化をおこなった。「同化」という言葉はここでいう政策にはふさわしくないかも知れないが、明治国家の政策は基本的に、かつては藩に対するアイデンティティを保持していた日本列島全体の人びとを同化しようとしたのである。蝦夷すなわち北海道と琉球すなわち沖縄を獲得したことによって、私が「周辺植民地政策」と呼ぶ政策を採用したのである。そこでの経験は日本政府が明治時代後期に台湾を獲得した際に適用した政策と共通の特徴を有している。
第3−5章:ここでは植民地政策がどのように朝鮮半島に適用されたかを考察する。第3章は1919年3月1日の独立運動の時期を扱っている。第4章はこの運動が日本人の認識をどのように変えたのかに注目している。このころから植民地政策にたいする支持とともに、(1800年代前後からのヨーロッパと同様に)同化は劣った人びととともに進めるには、不可能ではないにしても困難な政策であるという否定的な見方が広がった。
第5章は1930年代から40年代を考察している。この時期、日本がアジアにおける戦争を遂行するために朝鮮のより広範な協力を必要とした戦時期の状況のゆえに、同化についての確信がよみがえったと思われる。この時期をつうじて、日本人男性が日本軍に入隊するために朝鮮半島における仕事から離れたために、朝鮮人の割合は拡大した。ここまでの3つの章を通じて、日本の教育政策が最も注目される。というのも、もし同化が本気になって実行されたならば、同化される人びとは教育が自分たちを本国の人びとすなわち日本人の水準に引き上げると考えたからである。朝鮮(だけではなくアイヌや琉球、台湾の人びとに対しても)に導入された教育が低い水準のものであったことは、第1章で論じたように、ヨーロッパや米国など他の周辺植民地政策においてもよく見られたことであった。
第6章:この最終章では日本の同化政策にたいする朝鮮人の反応を考察している。まず、三一独立運動後の改革として導入された朝鮮語メディアの反日の声とそれらがどのように同化政策を批判しているかを論じ、続いて日本の植民地支配を受入れた「親日派」の声を紹介している。彼らは同化政策にどのような欠点を見出しているだろうか。日本の植民地支配当局にどのような示唆を与えているであろうか。
結論:この最終的な議論で、なぜ日本人は同化政策をさらに進めることができなかったかを論じている。なぜ、日本はヨーロッパで同化政策を行なった諸国が直面した、同化政策の論理と政策との間に存在する矛盾を克服することができなかったのか。日本の植民地支配の歴史は、たとえばアルジェリアにおけるフランスのそれよりも短かった。朝鮮における同化政策の最終的な結果を考えた日本人は、そのためには何世代も、50年、100年もかかるだろうと予想した。朝鮮総督府は前向きに進んでいることを示していただろうか。それとも、朝鮮人の戦時における社会的な進歩がさらに進行したら、日本人は戦争の終結後も朝鮮半島を保持し続けることができただろうか。結論としては、本研究はそのようにはならなかっただろうことを示している。
(原文は英語、五十嵐暁郎本学名誉教授訳)

2019年4月に石坂浩一編著『北朝鮮を知るための55章【第2版】』を明石書店から刊行した。編集にあたってくださった関正則さんも私も驚いたことに、早々に重版が決まった。日本の書店には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を普通に知ろうとするための一般書があまりなかったということだろうか。
この本の初版が出たのはキム・ジョンイル(金正日)国防委員長の時代、2006年であった。中国が場を設定した朝鮮半島をめぐる六者協議において2005年9月19日の共同声明が合意され、ようやく状況が安定するかと思われた矢先、欲を出したブッシュ・ジュニア政権が北朝鮮への圧迫を継続したため,北朝鮮は2006年10月9日に初めての核実験を行なった。結果を問われるのが政治の世界だとすれば、ブッシュ政権は朝鮮半島に関して失敗した政権になった。初版は9・19合意と核実験の間の時期に出版されたので、比較的楽観的な雰囲気でまとめられている。だが、現実は厳しくその後の朝鮮半島情勢はさまざまな葛藤を経験した。
本書は2014年に『現代韓国を知るための60章【第2版】』を出したころから、第2版の話が出ていた。およそ初版と同じ執筆者で同様の執筆分担をし、その後の状況を大幅に書き加えて出すことになった。ただ、2017年にトランプ政権が成立すると朝鮮半島は緊張の度を高め、18年には一転して対話局面に入った。本を注意深くお読みくださった方はお分かりだろうが、本の内容はおおよそ2017年の米朝対峙の時点でまとめられている。ところが、その後南北朝鮮の対話と米朝の歴史的首脳会談で状況は一変し、そのまま出版するわけにはいかなくなった。ちょうど昨18年は11月に刊行した金孝淳著『祖国が棄てた人びと』の監訳作業の完成が急務になったので、本書が日の目を見るのは2019年になってしまった。
これ以上引き延ばすと、もう全面的に書き換えざるを得なくなる。継ぎ足し的なところがあるが潮時だと思い、19年に入って仕上げを急ぎ出版にこぎつけた。少し長めの序章を加え2018年の状況を盛り込んで、本文中の修正は最低限にとどめた。本の「はじめに」でも記したが、原稿を早くから寄せてくださった文化関連の原稿をくださった皆様にはお詫びしなくてはならない。また、明石書店編集部の関正則さんには本当にお世話になり感謝している。
今日、時代はキム・ジョンウン(金正恩)国務委員長の時代になった。故キム・イルソン(金日成)主席の威光を活用しようとしているとはいえ、新しい時代の指導者は新しい状況に対応するビジョンを持っているはずである。そのビジョンや政治の特徴について、わかる限りのことをまとめさせていただいた。ゲームやアニメーションの世界では、時に「世界征服を狙う悪者」というキャラクターが登場する。日本ではキム・ジョンウンに対してこうした荒唐無稽なイメージを持つ人びとが少なくないのではないかと感じることがある。だが、北朝鮮は架空のものではなく現実である。当たり前のことだが、北朝鮮は世界征服など唱えたことは一度もないし、何をするかわからない国でもない。そして、70年にわたって政治権力として続いてきたということは、単なる圧政だけでは説明できない求心力があるはずだ。客観的研究が必要なゆえんである。戯画化したイメージで相手を侮蔑するだけでは、日本社会自身に前向きな成果をもたらすことができない。
私はもともと韓国社会や歴史を研究してきた者なので、北朝鮮研究は専門ではなかった。しかし、日本の市民運動の中で日朝国交正常化という平和のための当然の課題を前にして、わかりやすい解説書を書く人はそれほどいなかった。21世紀に入る中でだんだんと北朝鮮についての説明を求められる機会が増える中で初版の『51章』を書くことになったのである。ただ、まったく縁もゆかりもなかったわけでもない。元来、私の研究の出発点が日本人社会主義者の朝鮮認識というテーマであったので、社会主義についての一定の知識はあった。また、『祖国が棄てた人びと』で記録された在日韓国人政治犯の支援運動に関しては古くからの関わりがあったので、南北分断については意識せざるをえなかった。そして、韓国の平和研究、分断体制研究から多くのことを学び、そうした脈絡で「東北アジアに非核・平和の確立を!日朝国交正常化を求める連絡会」の共同代表に名を連ねることとなった。
日本社会では2002年の日朝首脳会談で日本人拉致が確認されて以来、北朝鮮についての冷静な議論が失われてしまったように見える。冷静な議論があってこそ、さまざまな懸案を解決することができるはずだが、そのようになっていないのは残念である。そればかりか、政治家が政権の維持のために「北朝鮮の脅威」を利用している。「北朝鮮のおかげで選挙に勝てた」と与党政治家が公言するようになっているのは憂慮すべきことではないのか。さまざまな視点から北朝鮮を分析する必要があるが、マスコミはそれをほとんど掘り下げていない。ある意味で、北朝鮮という外国の問題が日本のあり方を試す試金石になっているといえようか。
ある程度年齢が上の世代はお分かりだろうが、社会主義体制においては、党による政治への指導というのは当然のことである。そして、アジアの社会主義において「自力更生」や「自主」は重要な概念である。歴史と概念を踏まえて理解し、評価はそのあとに各自が考えればいい。とはいえ、はじめから北朝鮮の人びとを侮蔑の対象と見ていては、東北アジアでの日本の未来はない。
日本の平和な未来を創ろうとすれば、東北アジアでの地域協力は欠かすことができない。そのためには隣国と国交がないという異常な状態を変えなくてはいけない。2002年の日朝平壌宣言において、植民地支配への謝罪と平和に向けた協力に日朝が合意したにもかかわらず、その後の関係は進展しないままだ。地域の隣人として共存するためには、北朝鮮がどういう国でどういう人びとが暮らしているかを冷静に知っておかないと、社会的合意形成はできないだろう。北朝鮮の人びとは米国や関係国が自分たちを軍事的に圧迫し、存在を脅かしていると感じている。朝鮮戦争では全土が焦土化され、北朝鮮の人びとは忘れがたい恐怖に襲われ、いやしがたい傷を負った。その記憶は今も折に触れてよみがえる。そう感じているのは、指導層だけではなく、かの地の普通の人びとに他ならない。その人びとをよりよく知り、平和に出会う道を探ってこそ、日本は平和な社会であり続けられるのではないだろうか。日本社会で本書が少しでもお役に立てれば幸いである。
この本の初版が出たのはキム・ジョンイル(金正日)国防委員長の時代、2006年であった。中国が場を設定した朝鮮半島をめぐる六者協議において2005年9月19日の共同声明が合意され、ようやく状況が安定するかと思われた矢先、欲を出したブッシュ・ジュニア政権が北朝鮮への圧迫を継続したため,北朝鮮は2006年10月9日に初めての核実験を行なった。結果を問われるのが政治の世界だとすれば、ブッシュ政権は朝鮮半島に関して失敗した政権になった。初版は9・19合意と核実験の間の時期に出版されたので、比較的楽観的な雰囲気でまとめられている。だが、現実は厳しくその後の朝鮮半島情勢はさまざまな葛藤を経験した。
本書は2014年に『現代韓国を知るための60章【第2版】』を出したころから、第2版の話が出ていた。およそ初版と同じ執筆者で同様の執筆分担をし、その後の状況を大幅に書き加えて出すことになった。ただ、2017年にトランプ政権が成立すると朝鮮半島は緊張の度を高め、18年には一転して対話局面に入った。本を注意深くお読みくださった方はお分かりだろうが、本の内容はおおよそ2017年の米朝対峙の時点でまとめられている。ところが、その後南北朝鮮の対話と米朝の歴史的首脳会談で状況は一変し、そのまま出版するわけにはいかなくなった。ちょうど昨18年は11月に刊行した金孝淳著『祖国が棄てた人びと』の監訳作業の完成が急務になったので、本書が日の目を見るのは2019年になってしまった。
これ以上引き延ばすと、もう全面的に書き換えざるを得なくなる。継ぎ足し的なところがあるが潮時だと思い、19年に入って仕上げを急ぎ出版にこぎつけた。少し長めの序章を加え2018年の状況を盛り込んで、本文中の修正は最低限にとどめた。本の「はじめに」でも記したが、原稿を早くから寄せてくださった文化関連の原稿をくださった皆様にはお詫びしなくてはならない。また、明石書店編集部の関正則さんには本当にお世話になり感謝している。
今日、時代はキム・ジョンウン(金正恩)国務委員長の時代になった。故キム・イルソン(金日成)主席の威光を活用しようとしているとはいえ、新しい時代の指導者は新しい状況に対応するビジョンを持っているはずである。そのビジョンや政治の特徴について、わかる限りのことをまとめさせていただいた。ゲームやアニメーションの世界では、時に「世界征服を狙う悪者」というキャラクターが登場する。日本ではキム・ジョンウンに対してこうした荒唐無稽なイメージを持つ人びとが少なくないのではないかと感じることがある。だが、北朝鮮は架空のものではなく現実である。当たり前のことだが、北朝鮮は世界征服など唱えたことは一度もないし、何をするかわからない国でもない。そして、70年にわたって政治権力として続いてきたということは、単なる圧政だけでは説明できない求心力があるはずだ。客観的研究が必要なゆえんである。戯画化したイメージで相手を侮蔑するだけでは、日本社会自身に前向きな成果をもたらすことができない。
私はもともと韓国社会や歴史を研究してきた者なので、北朝鮮研究は専門ではなかった。しかし、日本の市民運動の中で日朝国交正常化という平和のための当然の課題を前にして、わかりやすい解説書を書く人はそれほどいなかった。21世紀に入る中でだんだんと北朝鮮についての説明を求められる機会が増える中で初版の『51章』を書くことになったのである。ただ、まったく縁もゆかりもなかったわけでもない。元来、私の研究の出発点が日本人社会主義者の朝鮮認識というテーマであったので、社会主義についての一定の知識はあった。また、『祖国が棄てた人びと』で記録された在日韓国人政治犯の支援運動に関しては古くからの関わりがあったので、南北分断については意識せざるをえなかった。そして、韓国の平和研究、分断体制研究から多くのことを学び、そうした脈絡で「東北アジアに非核・平和の確立を!日朝国交正常化を求める連絡会」の共同代表に名を連ねることとなった。
日本社会では2002年の日朝首脳会談で日本人拉致が確認されて以来、北朝鮮についての冷静な議論が失われてしまったように見える。冷静な議論があってこそ、さまざまな懸案を解決することができるはずだが、そのようになっていないのは残念である。そればかりか、政治家が政権の維持のために「北朝鮮の脅威」を利用している。「北朝鮮のおかげで選挙に勝てた」と与党政治家が公言するようになっているのは憂慮すべきことではないのか。さまざまな視点から北朝鮮を分析する必要があるが、マスコミはそれをほとんど掘り下げていない。ある意味で、北朝鮮という外国の問題が日本のあり方を試す試金石になっているといえようか。
ある程度年齢が上の世代はお分かりだろうが、社会主義体制においては、党による政治への指導というのは当然のことである。そして、アジアの社会主義において「自力更生」や「自主」は重要な概念である。歴史と概念を踏まえて理解し、評価はそのあとに各自が考えればいい。とはいえ、はじめから北朝鮮の人びとを侮蔑の対象と見ていては、東北アジアでの日本の未来はない。
日本の平和な未来を創ろうとすれば、東北アジアでの地域協力は欠かすことができない。そのためには隣国と国交がないという異常な状態を変えなくてはいけない。2002年の日朝平壌宣言において、植民地支配への謝罪と平和に向けた協力に日朝が合意したにもかかわらず、その後の関係は進展しないままだ。地域の隣人として共存するためには、北朝鮮がどういう国でどういう人びとが暮らしているかを冷静に知っておかないと、社会的合意形成はできないだろう。北朝鮮の人びとは米国や関係国が自分たちを軍事的に圧迫し、存在を脅かしていると感じている。朝鮮戦争では全土が焦土化され、北朝鮮の人びとは忘れがたい恐怖に襲われ、いやしがたい傷を負った。その記憶は今も折に触れてよみがえる。そう感じているのは、指導層だけではなく、かの地の普通の人びとに他ならない。その人びとをよりよく知り、平和に出会う道を探ってこそ、日本は平和な社会であり続けられるのではないだろうか。日本社会で本書が少しでもお役に立てれば幸いである。
立教大学異文化コミュニケーション学部准教授 石坂浩一