OBJECTIVE.
3月23日(金)・3月24日(土)の2日間、池袋キャンパスのタッカーホールにて、2017年度卒業式・大学院学位授与式が執り行われ、4,655人の卒業生(学部4,340人、大学院315人) が新しい門出を迎えました。2日間とも快晴に恵まれ、桜咲く青空のもと、新たな門出を祝う卒業生や保護者などでキャンパスは賑わいました。
式では、吉岡知哉総長より、学位記の授与とお祝いの式辞が述べられ、来賓の方々から祝辞が述べられました。
吉岡知哉総長の式辞
2018年3月23日
立教大学総長 吉岡 知哉
この春、立教大学は、4,340名に「学士」の学位を授与し、本学の卒業生として送り出します。皆さん、卒業おめでとうございます。
7年前、3月11日におきた東日本大震災とそれに続く東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、立教大学はその年の卒業式と入学式を行うことができませんでした。また、余震が続く中、新年度の授業開始もひと月遅らせなければなりませんでした。
皆さんたちのうちの多くは、この年、中学校を卒業して高校へと進学した学年です。被災して卒業式どころではなかった人もいるに違いありません。関東以北では、中学校の卒業式、高校の入学式が中止されたり延期されたりしたところも多いのではないかと思います。
西日本であれば、直接の影響はなかったかもしれませんが、連日のニュースで流れる映像はわすれることのできないものでしょう。皆さんたちの中には、阪神淡路大震災の年に生まれた人もいます。ご家族からその時の経験と記憶をあらためて聞かされたのではないでしょうか。
東日本大震災は、日常というものがいかに危うい基盤のうえになりたっているか、ということを示しました。同時に、人間の生き方、社会の在り方、近代文明の意義について、根底的に考える必要を迫ったのです。知性の府である大学はその責務を負っています。立教大学の構成員として学生時代を過ごした皆さんは、この間に学んだこと、考えたことをこれからもさらに深めていってください。
本日、卒業式という機会にお話ししておきたいのは、言葉についてです。
言葉とは何か。言葉はしばしば、コミュニケーションの手段、道具というふうに言われます。しかし少し考えてみればわかることですが、言葉は単なる道具、媒介手段ではありません。コミュニケーションの場合も、なにか伝えるべきものがあらかじめ存在していて、それを言葉によって相手に渡すわけではありません。伝えるべきもの自体が言葉によって構成されているので、内容と手段とが分かれるわけではないのです。
赤ちゃんは周囲の他者の眼差しの中で自分を形成していくと言われますが、同時に、他者から繰り返し話しかけられる言葉によって、世界を切り分ける切り分け方を身につけ、人間になっていくのです。
人間は言葉によって世界を切り分け、世界と自分とを関係づけていきます。言葉が個々の人間よりも先に存在していることを考えれば、言葉が人間を世界に関係づけるのだと言ったほうがよいかもしれません。言葉とは関係そのものであり、人間は言葉によって作られていると言うこともできます。
大学が人間社会のなかで果たす最大の役割は、物事を根底から徹底的に考えることにあります。考えるという営みは言葉によって成り立っています。したがって、大学における研究教育の最も重要な機能は、言葉を鍛えることだと言っても過言ではないでしょう。
言葉が人間社会において持つ意味を鮮烈に描き出したのが、ジョージ・オーウェルの『1984年』(Nineteen Eighty-Four)(*)です。
1984年という年は既に30年以上前に過ぎてしまいましたが、これが近未来の全体主義体制を描いた小説であることはご存知だろうと思います。
この小説の全体主義体制を支えているのが、Newspeakと呼ばれる言語体系とそれと連動するDoublethink(二重思考)です。
Newspeakは簡略化された英語で、Ingsocと呼ばれるこの国のイデオロギーを表現するためだけでなく、それ以外の思考法自体を不可能にするものであるとされます。
例えば、freeという単語は、Newspeakの中になお存在していますが、'This dog is free from lice'「この犬はシラミから自由である」とか、'This field is free from weeds'「この畑は雑草から自由である」といった用法でしか使うことができません。古い意味での'politically free'「政治的に自由」であるとか、'intellectually free'「知的に自由」というような使い方はできないのです。
なぜなら、political freedomやintellectual freedomは、現実にはもちろん、もはや概念としても存在せず、したがって当然ながら言い表すこと自体ができなくなっているからです。
同様に、'All mans are equal'(Newspeakではmanの複数形はmansとなります)「あらゆる人間は平等である」という文は、文として成立はするけれども、それは、'All men are redhaired'「あらゆる人間は赤毛である」という文が明白に誤りであるのと同様に、単なる誤りでしかないのです。
このように言葉を単純化し、意味と機能を縮小して行くのと併行して、思考方法自体の操作が行われます。それが二重思考Doublethinkです。
二重思考とは、「一つの精神が同時に相矛盾する2つの信条を持ち、その両方を受け入れる能力のこと」(p.274)を言います。それは意識的であり、かつ無意識的でなければなりません。
「一方で心から信じていながら意識的な嘘を付く事、不都合になった事実はどんなものでも忘れ去る事、次いで再びそれが必要となれば、必要な間だけ忘却の彼方から呼び戻す事、客観的事実の存在を否定すること、しかもその間ずっと自分の否定した事実を考慮している事−−−以上は全て不可欠な必須条件なのだ。二重思考という用語を用いる場合もまた二重思考によって行わねばならない。その言葉を用いるだけでも、事実を変造しているという事実を認めることになるからだ。そして二重思考の新たな行為を起こすことで、この認識を払拭するのである。」(p.275)
二重思考が可能になることで、この国の中心的機関である「真理省」(Oldspeakではthe Ministry of Truth、NewspeakではMINITRUE)は、記憶の整理と記録文書の変造を不断に行うことで、過去を思い通りに都合良く作り変え、しかもそのこと自体を忘却することができるのです。
この国家の有名なスローガン、'WAR IS PEACE FREEDOM IS SLAVERY IGNORANCE IS STRENGTH'もまた、二重思考の典型例であることは言うまでもないでしょう。
もっとも、『1984年』という小説は、入れ子のような構造になっていて、二重思考についての説明自体が、二重思考の産物であることを否定できないことも付け加えておかなければなりません。
ジョージ・オーウェルが今からちょうど70年前の1948年に執筆した『1984年』というディストピア小説をどう読むかについてはここでは触れません。しかし、人間が自由な存在であるためには、言葉が自由で豊かでなければならないことは確かです。言葉が貧困になれば、それと同時に自由は失われていくことでしょう。恐ろしいのは、自由が失われていくということ自体が意識されなくなっていくことです。
それを防ぎ、自由であり続けるためには、言葉を鍛え、思考力を強めていかなければなりません。
大学の授業はまさに多様な言葉によって成立しています。図書館には人類が積み重ねてきた言葉が溢れています。大学という空間はこれらの言葉によって、護られているのです。
しかしこれから皆さんは大学から新しい一歩を踏み出して行きます。そのとき、これまで自分の中に蓄積してきた言葉の力が問われるでしょう。自分の自由、仲間の自由、そして社会の自由を護り、発展させて行くために、これからも本を読み、学び続けてください。
15の春に東日本大震災を経験した中学生が、今年大学を卒業していくことに、深い感慨を覚えざるをえません。
この春、私も総長の任期が終わり、同時に定年を迎えるため、皆さんと一緒に立教大学を卒業することになります。今日の卒業式を、深く記憶に留めたいと思います。
卒業おめでとうございます。
みなさんとともに、新しい一歩を踏み出すことを本当にうれしく思います。
(*)George Orwell,Nineteen Eighty-Four, 新庄哲夫訳『1984年』ハヤカワ文庫。訳は一部変更している。
立教大学総長 吉岡 知哉
この春、立教大学は、4,340名に「学士」の学位を授与し、本学の卒業生として送り出します。皆さん、卒業おめでとうございます。
7年前、3月11日におきた東日本大震災とそれに続く東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響で、立教大学はその年の卒業式と入学式を行うことができませんでした。また、余震が続く中、新年度の授業開始もひと月遅らせなければなりませんでした。
皆さんたちのうちの多くは、この年、中学校を卒業して高校へと進学した学年です。被災して卒業式どころではなかった人もいるに違いありません。関東以北では、中学校の卒業式、高校の入学式が中止されたり延期されたりしたところも多いのではないかと思います。
西日本であれば、直接の影響はなかったかもしれませんが、連日のニュースで流れる映像はわすれることのできないものでしょう。皆さんたちの中には、阪神淡路大震災の年に生まれた人もいます。ご家族からその時の経験と記憶をあらためて聞かされたのではないでしょうか。
東日本大震災は、日常というものがいかに危うい基盤のうえになりたっているか、ということを示しました。同時に、人間の生き方、社会の在り方、近代文明の意義について、根底的に考える必要を迫ったのです。知性の府である大学はその責務を負っています。立教大学の構成員として学生時代を過ごした皆さんは、この間に学んだこと、考えたことをこれからもさらに深めていってください。
本日、卒業式という機会にお話ししておきたいのは、言葉についてです。
言葉とは何か。言葉はしばしば、コミュニケーションの手段、道具というふうに言われます。しかし少し考えてみればわかることですが、言葉は単なる道具、媒介手段ではありません。コミュニケーションの場合も、なにか伝えるべきものがあらかじめ存在していて、それを言葉によって相手に渡すわけではありません。伝えるべきもの自体が言葉によって構成されているので、内容と手段とが分かれるわけではないのです。
赤ちゃんは周囲の他者の眼差しの中で自分を形成していくと言われますが、同時に、他者から繰り返し話しかけられる言葉によって、世界を切り分ける切り分け方を身につけ、人間になっていくのです。
人間は言葉によって世界を切り分け、世界と自分とを関係づけていきます。言葉が個々の人間よりも先に存在していることを考えれば、言葉が人間を世界に関係づけるのだと言ったほうがよいかもしれません。言葉とは関係そのものであり、人間は言葉によって作られていると言うこともできます。
大学が人間社会のなかで果たす最大の役割は、物事を根底から徹底的に考えることにあります。考えるという営みは言葉によって成り立っています。したがって、大学における研究教育の最も重要な機能は、言葉を鍛えることだと言っても過言ではないでしょう。
言葉が人間社会において持つ意味を鮮烈に描き出したのが、ジョージ・オーウェルの『1984年』(Nineteen Eighty-Four)(*)です。
1984年という年は既に30年以上前に過ぎてしまいましたが、これが近未来の全体主義体制を描いた小説であることはご存知だろうと思います。
この小説の全体主義体制を支えているのが、Newspeakと呼ばれる言語体系とそれと連動するDoublethink(二重思考)です。
Newspeakは簡略化された英語で、Ingsocと呼ばれるこの国のイデオロギーを表現するためだけでなく、それ以外の思考法自体を不可能にするものであるとされます。
例えば、freeという単語は、Newspeakの中になお存在していますが、'This dog is free from lice'「この犬はシラミから自由である」とか、'This field is free from weeds'「この畑は雑草から自由である」といった用法でしか使うことができません。古い意味での'politically free'「政治的に自由」であるとか、'intellectually free'「知的に自由」というような使い方はできないのです。
なぜなら、political freedomやintellectual freedomは、現実にはもちろん、もはや概念としても存在せず、したがって当然ながら言い表すこと自体ができなくなっているからです。
同様に、'All mans are equal'(Newspeakではmanの複数形はmansとなります)「あらゆる人間は平等である」という文は、文として成立はするけれども、それは、'All men are redhaired'「あらゆる人間は赤毛である」という文が明白に誤りであるのと同様に、単なる誤りでしかないのです。
このように言葉を単純化し、意味と機能を縮小して行くのと併行して、思考方法自体の操作が行われます。それが二重思考Doublethinkです。
二重思考とは、「一つの精神が同時に相矛盾する2つの信条を持ち、その両方を受け入れる能力のこと」(p.274)を言います。それは意識的であり、かつ無意識的でなければなりません。
「一方で心から信じていながら意識的な嘘を付く事、不都合になった事実はどんなものでも忘れ去る事、次いで再びそれが必要となれば、必要な間だけ忘却の彼方から呼び戻す事、客観的事実の存在を否定すること、しかもその間ずっと自分の否定した事実を考慮している事−−−以上は全て不可欠な必須条件なのだ。二重思考という用語を用いる場合もまた二重思考によって行わねばならない。その言葉を用いるだけでも、事実を変造しているという事実を認めることになるからだ。そして二重思考の新たな行為を起こすことで、この認識を払拭するのである。」(p.275)
二重思考が可能になることで、この国の中心的機関である「真理省」(Oldspeakではthe Ministry of Truth、NewspeakではMINITRUE)は、記憶の整理と記録文書の変造を不断に行うことで、過去を思い通りに都合良く作り変え、しかもそのこと自体を忘却することができるのです。
この国家の有名なスローガン、'WAR IS PEACE FREEDOM IS SLAVERY IGNORANCE IS STRENGTH'もまた、二重思考の典型例であることは言うまでもないでしょう。
もっとも、『1984年』という小説は、入れ子のような構造になっていて、二重思考についての説明自体が、二重思考の産物であることを否定できないことも付け加えておかなければなりません。
ジョージ・オーウェルが今からちょうど70年前の1948年に執筆した『1984年』というディストピア小説をどう読むかについてはここでは触れません。しかし、人間が自由な存在であるためには、言葉が自由で豊かでなければならないことは確かです。言葉が貧困になれば、それと同時に自由は失われていくことでしょう。恐ろしいのは、自由が失われていくということ自体が意識されなくなっていくことです。
それを防ぎ、自由であり続けるためには、言葉を鍛え、思考力を強めていかなければなりません。
大学の授業はまさに多様な言葉によって成立しています。図書館には人類が積み重ねてきた言葉が溢れています。大学という空間はこれらの言葉によって、護られているのです。
しかしこれから皆さんは大学から新しい一歩を踏み出して行きます。そのとき、これまで自分の中に蓄積してきた言葉の力が問われるでしょう。自分の自由、仲間の自由、そして社会の自由を護り、発展させて行くために、これからも本を読み、学び続けてください。
15の春に東日本大震災を経験した中学生が、今年大学を卒業していくことに、深い感慨を覚えざるをえません。
この春、私も総長の任期が終わり、同時に定年を迎えるため、皆さんと一緒に立教大学を卒業することになります。今日の卒業式を、深く記憶に留めたいと思います。
卒業おめでとうございます。
みなさんとともに、新しい一歩を踏み出すことを本当にうれしく思います。
(*)George Orwell,Nineteen Eighty-Four, 新庄哲夫訳『1984年』ハヤカワ文庫。訳は一部変更している。
2018年3月24日
立教大学総長 吉岡 知哉
本日、立教大学は、31名に博士、17名に法務博士、315名に修士の学位を授与いたしました。課程博士21名のうち3名、修士のうち84名が外国人留学生、論文博士10名のうち1名が外国籍です。
学位を取得された皆さん、おめでとうございます。
皆さんの中には、今後もアカデミアの世界に残ろうと考えている人もいるでしょうし、そこから卒業して、いわゆる一般社会で活躍しようと計画している人もいることと思います。いずれにしても、他の人たちよりも長く、そして深く大学に関わってきた皆さんとともに、この折に大学という存在について、少し振り返ってみたいと思います。
大学とは何か、ということを考えるための手がかりとして、ここでは、大学をめぐるさまざまな言説を基礎付けている、3つのごくありふれた思考について触れておきます。これまでも、そしてこれからも、皆さんはこれらの思考に繰り返し出会うことと思いますが、立教大学は、これらの思考に抗して自らの教育の理念を組み立ててきたのです。
その第1は「大学は学費の対価として知識・技能を獲得する場である」というものです。
この考え方によれば、教員は知識・技能の売り手、学生はその買い手ということになります。重要なのは、ここでは知識・技能はいわばひとまとまりの物、パッケージ商品として受け渡されると看做されている点であり、いかにその売買と授受が効率的かつ適正に行われるかが関心の的となります。顧客である学生、あるいはその保護者にとっては、学費相応の知識・技能を得られるか、資格を取得することができるかが、大学に対する評価の基準となるでしょう。
またこれは、研究と教育とを分離してとらえ、研究は知識の開発・獲得であり、教育はその一方向的な伝達であるとする考え方とも通底していますし、研究者と教員とを分けるべきであるという議論にも繋がっています。
しかし大学教育で必要なことは、既存の知識・技能の伝授にとどまらず、ものごとの見方、考え方を学生に身につけさせることです。そのためには知識・技能の元となる現象、事実を取扱い、それについて考察するという過程を踏ませなければなりません。ものごとの見方、考え方が学生に伝わるのは、教員と学生とが交換者として向き合うのではなく、対象となる現象、事実に共に向かうことを通じてなのです。
その過程は、教える側の教員に対しても、考察を深め、新しい視点に気づかせる機会を与えます。知識・技能も思考法も、狭義の研究のみならず、教育の過程を通じても変化し深められます。人に教えることを通じて新たな問題を発見した経験はここにいる誰にでもあるでしょう。
また教育という点からすると、必ずしも直接的な伝達効率の追求が効果的であるとは限りません。学生の質問に答えず各自の自主的な努力に任せる場面は教育においてはごく日常的なことです。むしろ「教えない」という局面が、思考力の育成には不可欠であると言っても良い。教育の現場は知識や技能の受け渡しとその効率化・適正化という枠組みでは捉えきれないのです。
それよりはむしろ、大学は過去から受け継ぐ知的遺産を次世代に贈与するという機能を果たす場であると考えた方が良いようにも思います。しかしその場合でも、知識・技能がなにかパッケージのようなものとしてイメージされることは避けなければなりません。
教育は交換、売買と異なるだけでなく、贈与とも異なる、独自の固有性を持つ人間的活動なのです。
第2の思考は、大学はその時々に適した人材を育成する場であるというものです。
この考え方は、往々にして、大学を製品生産の仕組みのように捉える見方に収斂します。その場合肝要とされるのは、卒業時に「学生の質」が担保されていることです。「卒業証書、学位記は品質証明書である」というのもよく耳にする表現です。
高品質の製品を産出するための過程で大切なのは、精度の高い「選別」のシステムです。しかし、学生は製品ではありません。一定の規格に従った学生を一律に生産することは、広い視野と深い洞察力と柔軟な思考力を育てるという大学教育の本質に反していますし、実際に大変困難なことです。それに、たとえそのような規格品としての人材が製造、選別できたとしても、そのような人材は思考が限られてしまい、用途においても有効期限においてもきわめて限定的にならざるをえないでしょう。なぜならば、想像力、構想力にはなによりも自由が必要だからです。
さらに、選別は選別されて振り落とされる人間をうみだします。そこには、大学あるいは社会は不適格とされた存在を包摂できるかという問題が生じます。
ある基準による選別がその存在の全生活までをも決定するような組織や社会は、無気力や怨恨を醸成するきわめて不安定で危険な組織であり社会であると言わなければなりません。大学は社会内の一存在として、社会全体のあり方を広い視野と長期的な視点で考察する責務を負っているのであり、選別の持つ社会的機能についても十分な検討を行わなければならないのです。
第3は、大学はサービスを提供する場であるという考え方です。
「大学はサービス産業である」という言い方は、これもごく普通に見られます。教育は学生を顧客とするサービスの一種であるとする場合、学生(あるいは保護者)の「満足度」が大切な指標とされることになります。
けれども、サービスが顧客の要望に速やかに応えることを目指すのに対して、教員は学生が望まないことを時には半ば強制的に教えることによって、学生の固定観念を打ち破らなければなりません。プラトンの『国家』のなかの「洞窟の比喩」には、真理を手にした人間が、仲間にもそれを伝えようとして激しい反発と抵抗を受ける場面が描かれています。教育は葛藤を本質とすると言っても良いでしょう。
それに、教育の成果は直ちに目に見える形で現れるわけではありません。20年後か30年後、場合によっては世代を超えることもあるし、本人に自覚されないことさえもあるのです。その意味でも、「顧客の満足度」という指標で教育の成果を測定することは不可能に近いのです。
大学を知識の売買の場としてとらえる捉え方も、ニーズに沿った人材養成の場とする考え方も、サービス産業とみなす見方も、どれも大学という場において展開されているダイナミックな人間的活動をとらえることはできません。言い換えると、わたしたちはまだ大学というもの、教育という人間活動をうまく理解できていないのです。
大学は、人類の知的な遺産を受け継ぎ、学問を通じて人を育てる場所であり、人を育てることを通じて学問を進歩させ受け渡す場です。大学とは学問の場であるという言い方は同語反復的ですが、あえて言えば、同語反復以上の客観的な定義をすることができないことこそが、大学という存在を特徴づけているのではないでしょうか。
大学の社会的な役割は、既存の知識や思考をその根本、根拠にまで遡って徹底的に考えることにあります。その作業はあらゆる規制や束縛、そして思考自体の前提から自由でなければなりません。その自由を保証するために大学という組織が存在するのです。そのために大学自体が自由で自立した存在でなければなりません。外的な抑圧に屈すること、ある前提を問わずに済ませること。それがどれほどの致命的な結果を生むかを、我々は既に熟知しているのです。
これからの大学は、種々多様な人々が、移動し結びつきながら組み上げていくネットワークの結節点となることでしょう。大学の枠や国境を超えて、予期せぬ出会いを組織していくことは、これからますます大切になって行きます。
そのためにも、大学から外に出た人間がまた大学に戻ってくるという回路を充実させて行く必要があります。4月から大学の外で活躍するみなさんのなかからも、数年後にまた戻ってくるひとが出てこられると思います。大切なことは、一人ひとりの知的な可能性を多様化、重層化していくことであり、これからの大学はそのことを中軸として構想して行く必要があるでしょう。
立教大学の教育課程は、大学院も学部も、単なる知識の売買の場ではないし、その時々の社会的要請あるいは企業の要求に沿った機能を備える人材を作るだけの場でもなく、顧客のニーズに直ちに応える便利なサービス機関でもありません。
そのような立教大学の大学院で、皆さんは、一人ひとりが問題を発見し、それを真摯に考え抜くという作業を積み重ねて、学位を取得しました。自分の力に自信と誇りをもって、次の一歩を踏み出してください。
改めてお祝いをもうしあげます。
学位の取得、おめでとうございます。
立教大学総長 吉岡 知哉
本日、立教大学は、31名に博士、17名に法務博士、315名に修士の学位を授与いたしました。課程博士21名のうち3名、修士のうち84名が外国人留学生、論文博士10名のうち1名が外国籍です。
学位を取得された皆さん、おめでとうございます。
皆さんの中には、今後もアカデミアの世界に残ろうと考えている人もいるでしょうし、そこから卒業して、いわゆる一般社会で活躍しようと計画している人もいることと思います。いずれにしても、他の人たちよりも長く、そして深く大学に関わってきた皆さんとともに、この折に大学という存在について、少し振り返ってみたいと思います。
大学とは何か、ということを考えるための手がかりとして、ここでは、大学をめぐるさまざまな言説を基礎付けている、3つのごくありふれた思考について触れておきます。これまでも、そしてこれからも、皆さんはこれらの思考に繰り返し出会うことと思いますが、立教大学は、これらの思考に抗して自らの教育の理念を組み立ててきたのです。
その第1は「大学は学費の対価として知識・技能を獲得する場である」というものです。
この考え方によれば、教員は知識・技能の売り手、学生はその買い手ということになります。重要なのは、ここでは知識・技能はいわばひとまとまりの物、パッケージ商品として受け渡されると看做されている点であり、いかにその売買と授受が効率的かつ適正に行われるかが関心の的となります。顧客である学生、あるいはその保護者にとっては、学費相応の知識・技能を得られるか、資格を取得することができるかが、大学に対する評価の基準となるでしょう。
またこれは、研究と教育とを分離してとらえ、研究は知識の開発・獲得であり、教育はその一方向的な伝達であるとする考え方とも通底していますし、研究者と教員とを分けるべきであるという議論にも繋がっています。
しかし大学教育で必要なことは、既存の知識・技能の伝授にとどまらず、ものごとの見方、考え方を学生に身につけさせることです。そのためには知識・技能の元となる現象、事実を取扱い、それについて考察するという過程を踏ませなければなりません。ものごとの見方、考え方が学生に伝わるのは、教員と学生とが交換者として向き合うのではなく、対象となる現象、事実に共に向かうことを通じてなのです。
その過程は、教える側の教員に対しても、考察を深め、新しい視点に気づかせる機会を与えます。知識・技能も思考法も、狭義の研究のみならず、教育の過程を通じても変化し深められます。人に教えることを通じて新たな問題を発見した経験はここにいる誰にでもあるでしょう。
また教育という点からすると、必ずしも直接的な伝達効率の追求が効果的であるとは限りません。学生の質問に答えず各自の自主的な努力に任せる場面は教育においてはごく日常的なことです。むしろ「教えない」という局面が、思考力の育成には不可欠であると言っても良い。教育の現場は知識や技能の受け渡しとその効率化・適正化という枠組みでは捉えきれないのです。
それよりはむしろ、大学は過去から受け継ぐ知的遺産を次世代に贈与するという機能を果たす場であると考えた方が良いようにも思います。しかしその場合でも、知識・技能がなにかパッケージのようなものとしてイメージされることは避けなければなりません。
教育は交換、売買と異なるだけでなく、贈与とも異なる、独自の固有性を持つ人間的活動なのです。
第2の思考は、大学はその時々に適した人材を育成する場であるというものです。
この考え方は、往々にして、大学を製品生産の仕組みのように捉える見方に収斂します。その場合肝要とされるのは、卒業時に「学生の質」が担保されていることです。「卒業証書、学位記は品質証明書である」というのもよく耳にする表現です。
高品質の製品を産出するための過程で大切なのは、精度の高い「選別」のシステムです。しかし、学生は製品ではありません。一定の規格に従った学生を一律に生産することは、広い視野と深い洞察力と柔軟な思考力を育てるという大学教育の本質に反していますし、実際に大変困難なことです。それに、たとえそのような規格品としての人材が製造、選別できたとしても、そのような人材は思考が限られてしまい、用途においても有効期限においてもきわめて限定的にならざるをえないでしょう。なぜならば、想像力、構想力にはなによりも自由が必要だからです。
さらに、選別は選別されて振り落とされる人間をうみだします。そこには、大学あるいは社会は不適格とされた存在を包摂できるかという問題が生じます。
ある基準による選別がその存在の全生活までをも決定するような組織や社会は、無気力や怨恨を醸成するきわめて不安定で危険な組織であり社会であると言わなければなりません。大学は社会内の一存在として、社会全体のあり方を広い視野と長期的な視点で考察する責務を負っているのであり、選別の持つ社会的機能についても十分な検討を行わなければならないのです。
第3は、大学はサービスを提供する場であるという考え方です。
「大学はサービス産業である」という言い方は、これもごく普通に見られます。教育は学生を顧客とするサービスの一種であるとする場合、学生(あるいは保護者)の「満足度」が大切な指標とされることになります。
けれども、サービスが顧客の要望に速やかに応えることを目指すのに対して、教員は学生が望まないことを時には半ば強制的に教えることによって、学生の固定観念を打ち破らなければなりません。プラトンの『国家』のなかの「洞窟の比喩」には、真理を手にした人間が、仲間にもそれを伝えようとして激しい反発と抵抗を受ける場面が描かれています。教育は葛藤を本質とすると言っても良いでしょう。
それに、教育の成果は直ちに目に見える形で現れるわけではありません。20年後か30年後、場合によっては世代を超えることもあるし、本人に自覚されないことさえもあるのです。その意味でも、「顧客の満足度」という指標で教育の成果を測定することは不可能に近いのです。
大学を知識の売買の場としてとらえる捉え方も、ニーズに沿った人材養成の場とする考え方も、サービス産業とみなす見方も、どれも大学という場において展開されているダイナミックな人間的活動をとらえることはできません。言い換えると、わたしたちはまだ大学というもの、教育という人間活動をうまく理解できていないのです。
大学は、人類の知的な遺産を受け継ぎ、学問を通じて人を育てる場所であり、人を育てることを通じて学問を進歩させ受け渡す場です。大学とは学問の場であるという言い方は同語反復的ですが、あえて言えば、同語反復以上の客観的な定義をすることができないことこそが、大学という存在を特徴づけているのではないでしょうか。
大学の社会的な役割は、既存の知識や思考をその根本、根拠にまで遡って徹底的に考えることにあります。その作業はあらゆる規制や束縛、そして思考自体の前提から自由でなければなりません。その自由を保証するために大学という組織が存在するのです。そのために大学自体が自由で自立した存在でなければなりません。外的な抑圧に屈すること、ある前提を問わずに済ませること。それがどれほどの致命的な結果を生むかを、我々は既に熟知しているのです。
これからの大学は、種々多様な人々が、移動し結びつきながら組み上げていくネットワークの結節点となることでしょう。大学の枠や国境を超えて、予期せぬ出会いを組織していくことは、これからますます大切になって行きます。
そのためにも、大学から外に出た人間がまた大学に戻ってくるという回路を充実させて行く必要があります。4月から大学の外で活躍するみなさんのなかからも、数年後にまた戻ってくるひとが出てこられると思います。大切なことは、一人ひとりの知的な可能性を多様化、重層化していくことであり、これからの大学はそのことを中軸として構想して行く必要があるでしょう。
立教大学の教育課程は、大学院も学部も、単なる知識の売買の場ではないし、その時々の社会的要請あるいは企業の要求に沿った機能を備える人材を作るだけの場でもなく、顧客のニーズに直ちに応える便利なサービス機関でもありません。
そのような立教大学の大学院で、皆さんは、一人ひとりが問題を発見し、それを真摯に考え抜くという作業を積み重ねて、学位を取得しました。自分の力に自信と誇りをもって、次の一歩を踏み出してください。
改めてお祝いをもうしあげます。
学位の取得、おめでとうございます。
祝辞
3月23日(金)
12:00 上原 榮正氏
(日本聖公会沖縄教区主教)
14:00、16:00 岸上 克彦氏
(アサヒ飲料株式会社代表取締役社長 1976年経済学部卒)
(日本聖公会沖縄教区主教)
14:00、16:00 岸上 克彦氏
(アサヒ飲料株式会社代表取締役社長 1976年経済学部卒)
3月24日(土)
09:30 和田 成史氏
(株式会社オービックビジネスコンサルタント代表取締役社長、立教大学校友会長 1975年経済学部卒)
11:30、13:30 毛呂 准子氏
(株式会社商船三井経営企画部専任部長 1986年文学部卒)
(株式会社オービックビジネスコンサルタント代表取締役社長、立教大学校友会長 1975年経済学部卒)
11:30、13:30 毛呂 准子氏
(株式会社商船三井経営企画部専任部長 1986年文学部卒)

卒業生・修了生たちで賑わう正門前の様子

吉岡総長の式辞
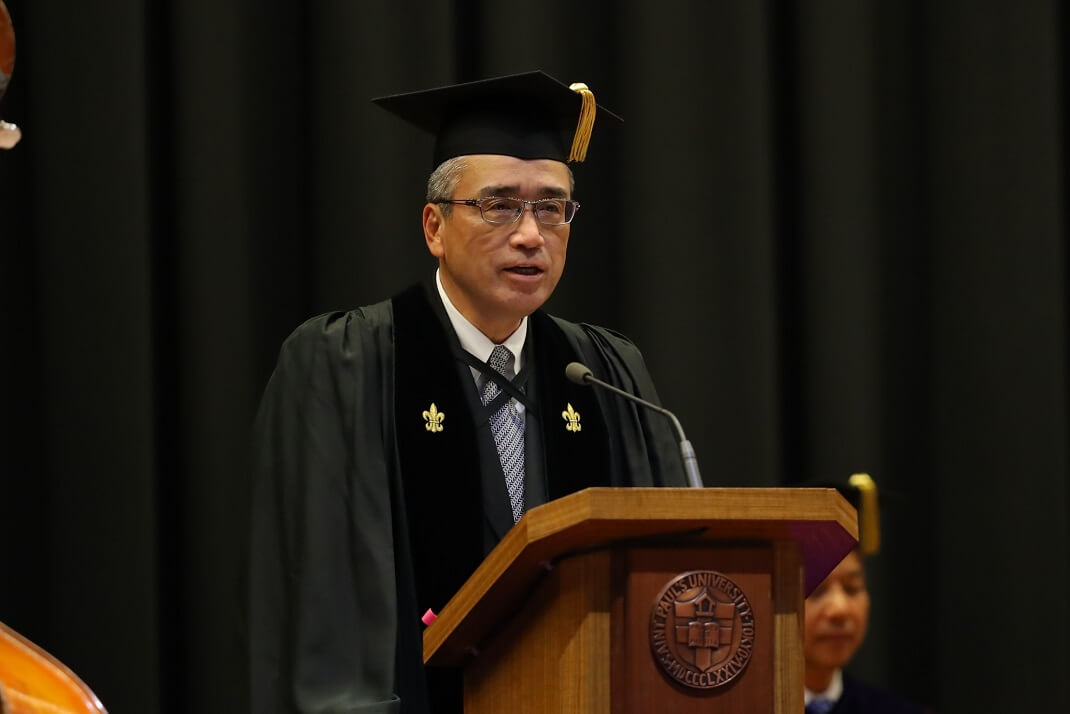
岸上克彦氏による祝辞

タッカーホールで行われた卒業式・大学院学位授与式の様子

桜咲くキャンパス内の様子

毛呂准子氏による祝辞

池袋チャペルでの卒業礼拝の様子

その他についての最新記事
-
2026/02/16 (MON)